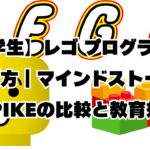小学生でもできる!Scratch(スクラッチ)プログラミングの始め方【初心者向け完全ガイド】 「小学校でプログラミングが必修になったけど、うちの子についていけるかな…」「私自身、プログラミングなんてやったことないのに、どうサポートすればいいの?」 2020年から小学校でプログラミング教育が必修化され…
小学生向けScratch(スクラッチ)の始め方|ブロックでゲームを作ろう【初心者完全ガイド】
- 公開日:2025/11/16
- 最終更新日:
- プログラミング
- 小学生向けScratch(スクラッチ)の始め方|ブロックでゲームを作ろう【初心者完全ガイド】 はコメントを受け付けていません

小学生向けScratch(スクラッチ)の始め方|ブロックでゲームを作ろう【初心者完全ガイド】
「プログラミングって難しそう…」「うちの子にもできるかな?」そんな不安を抱えている保護者の方も多いのではないでしょうか。
Scratch(スクラッチ)は、キーボードが打てない小学生でも、ブロックを組み合わせるだけで本格的なプログラミングが学べる無料教材です。この記事では、アカウント登録から基本操作、簡単なゲーム作りまで、お子さんと一緒に進められるよう丁寧に解説します。
この記事で作れるようになるもの:猫がサッカー場のゴールまで走り、ゴールしたら「ゴール!」と喋るゲーム
💡 お子さんの年齢に合わせた記事を選びましょう
この記事は小学3年生〜6年生を対象に、ループや条件分岐といったプログラミングの考え方を学びながらゲームを作る内容です。
未就学児〜小学2年生のお子さんには、もっと簡単な「体験重視」の記事をおすすめします:
👉 小学生でもできる!Scratch(スクラッチ)プログラミングの始め方【初心者向け完全ガイド】
Scratch(スクラッチ)とは?小学生におすすめな3つの理由
Scratchは、アメリカのマサチューセッツ工科大学(MIT)が開発した、子ども向けプログラミング教材です。世界中で使われており、日本の小学校のプログラミング教育でも広く活用されています。
①無料で使えて、キーボード入力不要
Scratchは完全無料で利用でき、特別なソフトをインストールする必要もありません。インターネットに接続できるパソコンやタブレットがあれば、今すぐ始められます。
また、従来のプログラミングのように英語のコードを打ち込む必要がないため、キーボードがまだ上手に打てない小学生でも安心して取り組めます。
②ブロックを組み合わせるだけでプログラムが作れる
Scratchでは、命令が書かれた「ブロック」をパズルのように組み合わせてプログラムを作ります。レゴブロックや積み木で遊ぶ感覚で、楽しみながらプログラミングの基礎が身につきます。
従来のプログラミング
✍️ 英語のコードを正確に入力
❌ スペルミスでエラーが出る
📚 専門知識が必要
🎯 対象:中学生以上
Scratch(スクラッチ)
🧩 ブロックをドラッグ&ドロップ
✅ 文法エラーが起きない
🎨 直感的に操作できる
🎯 対象:小学生から
③本格的なプログラミングの考え方が学べる
Scratchは見た目こそ可愛らしいですが、「ループ処理(繰り返し)」や「条件分岐(もし〜なら)」といった、プロのプログラマーも使う重要な考え方を学ぶことができます。
ここで身につけた論理的思考力は、将来本格的なプログラミング言語(Python、JavaScriptなど)を学ぶ際にも必ず役立ちます。
Scratchを始める準備|アカウント登録は必要?
登録なしでも遊べる「お試しモード」
Scratchはアカウント登録をしなくても、すぐにプログラミングを体験できます。最初は登録せずに気軽に触ってみて、「もっと続けたい!」と思ったら登録するという流れがおすすめです。
アカウント登録のメリット(作品保存・公開)
アカウントを作成すると、次のようなメリットがあります:
- 作品を保存できる:途中まで作ったゲームを保存して、後から続きを作れます
- 作品を公開できる:完成した作品を世界中の人に見てもらえます
- 他の人の作品を見られる:世界中のScratchユーザーの作品を見て、勉強できます
アカウント登録は無料で、メールアドレスがあれば簡単に作成できます。ただし、13歳未満のお子さんの場合は保護者の方のメールアドレスを使って登録することをおすすめします。
「作る」ボタンからスタート
Scratchの公式サイト(https://scratch.mit.edu/)にアクセスしたら、画面上部の「作る」というボタンをクリックしてください。これだけで、すぐにプログラミングを始められる画面に移動します。
✅ 始める前に確認しよう
- パソコンまたはタブレット(スマートフォンでも可能ですが、パソコン推奨)
- インターネット環境(Wi-Fiや有線LAN)
- 保護者の見守り(初回のみ、操作に慣れるまで)
- マウスまたはタッチパッド(タブレットの場合は指で操作)
Scratchの画面の見方|3つのエリアを覚えよう
Scratchの画面は、大きく分けて3つのエリアで構成されています。最初にこの3つの役割を理解しておくと、スムーズにプログラミングを進められます。
左側:ブロック置き場(命令の倉庫)
画面の左側には、プログラムで使える「ブロック」がずらりと並んでいます。このブロックは、色ごとにカテゴリー分けされています:
- 青色(動き):キャラクターを動かす命令
- 紫色(見た目):キャラクターの見た目を変える命令
- ピンク色(音):音を鳴らす命令
- オレンジ色(イベント):「旗が押されたとき」などのスタート命令
- 黄色(制御):繰り返しや条件分岐などの命令
- 水色(調べる):何かに触れたかなどを調べる命令
この「ブロック置き場」は、料理でいえば「食材庫」のようなものです。必要な材料(ブロック)を取り出して、料理(プログラム)を作っていきます。
真ん中:プログラミングエリア(作業スペース)
画面の真ん中は、ブロックを組み立ててプログラムを作る作業スペースです。左側から必要なブロックをドラッグ(クリックしたまま移動)して、ここに運んできます。
ブロック同士をくっつけることで、命令を順番に実行させることができます。まるでレシピを書くように、「最初にこれをして、次にこれをして…」という手順を組み立てていきます。
右側:実行エリア(結果が見える場所)
画面の右側には、プログラムを実行したときの結果が表示されます。真ん中で組み立てたプログラムが、ここで実際に動きます。
最初は「猫」のキャラクターが真ん中に立っていますが、プログラムを実行すると、この猫が動いたり喋ったりします。料理が完成して、実際に食べてみる場面に例えられます。
🎨 3つのエリアを料理に例えると
- 左側(ブロック置き場) = 食材庫(必要な材料を取り出す場所)
- 真ん中(プログラミングエリア) = キッチン(材料を組み合わせて料理を作る場所)
- 右側(実行エリア) = 食卓(完成した料理を味わう場所)
はじめてのプログラム|猫を10歩動かしてみよう
それでは、実際にプログラムを作ってみましょう。まずは簡単な「猫を10歩前に動かす」プログラムに挑戦します。
ステップ1:「イベント」ブロックで旗が押された時を設定
左側のブロック置き場から、オレンジ色の「イベント」というカテゴリーをクリックしてください。すると、オレンジ色のブロックがいくつか表示されます。
その中から、「🚩 が押されたとき」というブロックを見つけてください。このブロックは、「プログラムをスタートさせる合図」の役割を持っています。
このブロックをクリックしたまま、真ん中のプログラミングエリアまで運んでください(ドラッグ&ドロップ)。そこで手を離すと、ブロックが配置されます。
ステップ2:「動き」ブロックで10歩動かす命令
次に、左側のブロック置き場から、青色の「動き」というカテゴリーをクリックしてください。青色のブロックが表示されます。
その中から、「10歩動かす」というブロックを見つけて、先ほどと同じように真ん中のエリアに運んでください。
ステップ3:ブロックをくっつける方法
ここが重要なポイントです。2つのブロックをくっつけて、命令を繋げます。
オレンジ色のブロック(🚩 が押されたとき)の下には、小さな「出っ張り」があります。青色のブロック(10歩動かす)の上には、「へこみ」があります。
青色のブロックを、オレンジ色のブロックの出っ張りに近づけてみてください。すると、薄い影が表示されます。この影が見えたら、手を離してください。すると、2つのブロックが「カチッ」とくっつきます。
これで、「旗が押されたときに、10歩動かす」というプログラムが完成しました!
ステップ4:緑の旗を押して実行してみよう
画面右上に、緑色の旗のマークがあります。これをクリックしてみてください。
すると…猫が少しだけ前に動きましたか?もう一度旗をクリックすると、また少し動きます。これが、あなたが作った最初のプログラムです!
🚩 緑の旗が押される
スタートの合図
🐱 猫が10歩動く
命令が実行される
✅ プログラム終了
また旗を押すと繰り返す
🎯 プログラムを日常生活に例えると
この「旗が押されたとき→10歩動かす」というプログラムは、日常生活でいえば次のようなものです:
「先生が手を叩いたら(合図)→子どもが10歩前に歩く」
プログラミングとは、このように「いつ・何をするか」を順番に決めていく作業なのです。
ゲーム作りに挑戦!猫がゴールまで走るプログラム
基本操作が分かったところで、もう少し本格的なゲームを作ってみましょう。今回作るのは、「猫がサッカー場のゴールまで走り、ゴールしたら『ゴール!』と喋るゲーム」です。
このゲームを作ることで、プログラミングで最も重要な「ループ処理」と「条件分岐」という考え方を学ぶことができます。
ステップ1:サッカー場の背景を追加する
まず、舞台となる背景を設定します。画面右下に、「背景を選ぶ」というボタンがあります(画像のアイコン)。これをクリックしてください。
すると、たくさんの背景が表示されます。その中から、「スポーツ」というカテゴリーを選び、サッカー場の背景を選んでください。
これで、猫がサッカー場に立っている状態になりました。
ステップ2:「ずっと」ブロックでループ処理を学ぶ
先ほど作ったプログラムでは、旗を1回押すごとに猫が10歩動きました。でも、ゴールまで行くには何度も旗を押さなければなりません。
ここで登場するのが「ループ処理」です。ループとは「繰り返し」という意味で、同じ動作を自動的に何度も実行させることができます。
左側のブロック置き場から、黄色の「制御」というカテゴリーをクリックしてください。その中に、「ずっと」というブロックがあります。
この「ずっと」ブロックは、特殊な形をしています。上下にブロックを繋げられるだけでなく、中にブロックを入れることができます。
まず、先ほど作った「🚩 が押されたとき」と「10歩動かす」のブロックを一旦離してください。青いブロックをクリックして、少し横に移動させます。
次に、「ずっと」ブロックを、「🚩 が押されたとき」の下にくっつけます。
最後に、「10歩動かす」ブロックを、「ずっと」ブロックの中に入れてください。「ずっと」ブロックの内側に近づけると、影が表示されるので、そこで手を離します。
これで、「旗が押されたら、ずっと10歩動かし続ける」というプログラムになりました。
緑の旗を押してみてください。今度は、猫が止まらずにずっと歩き続けるはずです!
🔄 ループ処理を日常生活に例えると
ループ処理なし:「お母さんが『歯を磨きなさい』と言うたびに、1回だけ磨く」
ループ処理あり:「お母さんが『歯を磨きなさい』と言ったら、上下左右をずっと磨き続ける」
ループを使うことで、同じ動作を何度も自動的に繰り返すことができます。プログラミングでは、この「繰り返し」が非常に重要な考え方です。
⚠️ プログラムを止める方法
「ずっと」を使ったプログラムは、自動的には止まりません。猫がずっと動き続けてしまう場合は、緑の旗の隣にある赤い「停止」ボタンをクリックしてください。これでプログラムが止まります。
停止した後、猫をスタート位置に戻すには、猫をマウスでドラッグして移動させることができます。
ステップ3:「もし〜なら」で条件分岐を覚える
今のプログラムでは、猫がゴールに着いても、そのまま通り過ぎてしまいます。「ゴールに着いたら止まって喋る」ようにするには、「条件分岐」という考え方を使います。
条件分岐とは、「もし〜なら、◯◯をする」という条件付きの命令です。例えば、「もし雨が降っているなら、傘を持つ」というように、状況に応じて行動を変えることができます。
左側のブロック置き場から、再び黄色の「制御」カテゴリーを開いてください。その中に、「もし◯◯なら」というブロックがあります。このブロックも「ずっと」と同じように、中にブロックを入れることができます。
この「もし〜なら」ブロックを、「ずっと」ブロックの中、そして「10歩動かす」ブロックの下に配置してください。
ステップ4:端に触れたかを調べる
次に、「何を条件にするか」を設定します。今回は、「猫が画面の端(ゴール)に触れたか」を条件にします。
左側のブロック置き場から、水色の「調べる」というカテゴリーをクリックしてください。その中に、「◯◯に触れた」というブロックがあります。
このブロックは、少し形が違います。先が尖った六角形の形をしていて、「もし〜なら」ブロックの条件を入れる部分(六角形の穴)にぴったり合います。
「◯◯に触れた」ブロックを、「もし〜なら」ブロックの六角形の穴に入れてください。カチッとはまります。
次に、このブロックの「◯◯」の部分をクリックして、「端」を選んでください。これで、「もし端に触れたなら」という条件になります。
ステップ5:ゴールしたら「ゴール!」と喋らせる
最後に、ゴールに着いたときの動作を設定します。左側のブロック置き場から、紫色の「見た目」カテゴリーをクリックしてください。
その中に、「こんにちは!と言う」というブロックがあります。このブロックを、「もし端に触れたなら」ブロックの中に入れてください。
ブロックの中の「こんにちは!」という文字をクリックして、「ゴール!」に書き換えてください。
これで、プログラムが完成しました!
完成!プログラムを実行してみよう
猫をスタート位置(画面の左側)に戻して、緑の旗をクリックしてみてください。
猫がサッカー場を走り、ゴール(画面の右端)に着いたら「ゴール!」と喋るはずです。おめでとうございます!あなたは、ループ処理と条件分岐を使った本格的なプログラムを完成させました。
🚩 緑の旗が押される
プログラムスタート
🔄 ずっと繰り返す
ループ処理開始
🐱 10歩動かす
猫が前進
❓ もし端に触れたなら
条件チェック
💬 「ゴール!」と言う
条件が満たされた時の動作
🔄 ループに戻る
「ずっと」に戻って繰り返す
🏃 条件分岐を日常生活に例えると
「ずっと前に走り続ける。もしゴールに着いたなら、『やった!』と叫ぶ」
これは、運動会のかけっこと同じですね。ゴールに着くまではずっと走り続け、ゴールに着いたら(条件が満たされたら)、嬉しさを表現します。
プログラミングでは、このように「ある条件が満たされたときだけ、特定の動作をする」という仕組みをたくさん使います。
プログラミングの重要な考え方3つ
ここまでのゲーム作りを通して、プログラミングで最も重要な3つの考え方を学びました。これらは、どんなプログラミング言語を使う場合でも共通する基本概念です。
①ループ処理とは?(繰り返しで効率化)
ループ処理は、同じ動作を何度も繰り返す仕組みです。Scratchでは「ずっと」というブロックを使いました。
もしループがなかったら、「10歩動かす」ブロックを100個も200個も並べなければなりません。ループを使うことで、たった1つのブロックで無限に繰り返すことができます。
日常生活の例:
- 毎朝の歯磨き(上の歯を磨く→下の歯を磨く→うがいをする、を毎日繰り返す)
- 階段を登る(1段登る→また1段登る→…を繰り返す)
- お皿洗い(1枚洗う→また1枚洗う→…をお皿がなくなるまで繰り返す)
②条件分岐とは?(もし〜ならを使う)
条件分岐は、状況に応じて行動を変える仕組みです。Scratchでは「もし〜なら」というブロックを使いました。
条件分岐があることで、プログラムは「いつも同じ動きをする」だけでなく、「状況に合わせて賢く動く」ことができます。
日常生活の例:
- もし雨が降っているなら、傘を持つ
- もしお腹が空いているなら、ご飯を食べる
- もし信号が赤なら、止まる
- もしテストで100点を取ったなら、ご褒美をもらえる
③イベント処理とは?(何かが起きたら実行)
イベント処理は、「何かのきっかけで動作を始める」仕組みです。Scratchでは「🚩 が押されたとき」というブロックを使いました。
プログラムは、勝手に動き出すわけではありません。「旗が押された」「キーボードが押された」「キャラクターが何かに触れた」といった「イベント(出来事)」をきっかけに動き始めます。
日常生活の例:
- 目覚まし時計が鳴ったとき→起きる
- 先生が「起立」と言ったとき→立ち上がる
- お母さんが「ご飯よ」と呼んだとき→食卓に向かう
- チャイムが鳴ったとき→授業を始める
🔄 ループ処理
役割:繰り返し
Scratchのブロック:「ずっと」
使う場面:同じ動作を何度もする時
🔀 条件分岐
役割:状況判断
Scratchのブロック:「もし〜なら」
使う場面:条件によって動作を変える時
⚡ イベント処理
役割:きっかけ
Scratchのブロック:「🚩 が押されたとき」
使う場面:プログラムを始める時
この3つの考え方は、Python、JavaScript、Javaなど、どんなプログラミング言語でも使われる「プログラミングの共通言語」です。Scratchでこれらをマスターすれば、将来どんな言語を学ぶときも役立ちます。
プログラムが動かない時の確認ポイント
プログラムを作っていると、「あれ?動かない…」ということがあります。これは初心者だけでなく、プロのプログラマーでも日常的に経験することです。落ち込まずに、次のポイントを確認してみましょう。
ブロックが正しくくっついているか
最もよくあるミスは、ブロック同士がきちんとくっついていないことです。
ブロックをドラッグして移動させたときに、薄い影が表示されたかどうかを確認してください。影が表示されずに手を離すと、ブロックはくっつかずに別々のままになってしまいます。
もし離れてしまっている場合は、もう一度ブロックをドラッグして、影が表示されるまで近づけてからくっつけ直してください。
緑の旗を押したか
プログラムは、緑の旗を押さないと実行されません。ブロックを組み立てただけでは、まだ「設計図」を作っただけの状態です。
画面右上の緑の旗をクリックすることで、初めてプログラムが動き出します。これは、料理のレシピを書いただけでは料理ができないのと同じです。実際に作る(実行する)必要があります。
停止ボタンで一度リセットしてみる
「ずっと」を使ったプログラムは、一度動き始めると止まりません。何か変更を加えても、古いプログラムがまだ動き続けている可能性があります。
そんなときは、赤い停止ボタンを押して、プログラムを完全に止めてください。それから、もう一度緑の旗を押して、新しいプログラムを実行してみましょう。
⚠️ よくあるミスと対処法
- ミス1:ブロックが離れている → 影が出るまで近づけてからくっつける
- ミス2:「ずっと」の外にブロックを置いている → 「ずっと」の中に入れる
- ミス3:条件の六角形ブロックが入っていない → 「◯◯に触れた」を「もし〜なら」の穴に入れる
- ミス4:古いプログラムが動き続けている → 停止ボタンを押してリセット
- ミス5:キャラクターが画面の外に出てしまった → マウスでドラッグして戻す
大切なこと:プログラミングでは、失敗は恥ずかしいことではありません。むしろ、失敗から学ぶことが最も重要です。「なぜ動かないのか?」を考えて試行錯誤することで、プログラミングの力が身につきます。
もっと学びたい!Scratchのおすすめ学習リソース
基本的な使い方をマスターしたら、次はもっといろいろな作品作りに挑戦してみましょう。ここでは、Scratchを学び続けるためのおすすめのリソースを紹介します。
NHK「ワイワイプログラミング」で楽しく学ぶ
NHKが提供している「ワイワイプログラミング」は、Scratchを使った様々なゲームやアニメーションの作り方を、動画とウェブサイトで分かりやすく解説しています。
このサイトでは、約20種類のプロジェクトが紹介されており、それぞれに詳しい作り方の説明がついています。動画を見ながら一緒に作ることができるので、独学でも進めやすいのが特徴です。
- 宇宙を旅する冒険ゲーム
- 音楽を演奏できるプログラム
- クイズゲーム
- 迷路ゲーム
など、バラエティ豊かな内容が揃っています。「次は何を作ろうかな?」と迷ったら、このサイトを覗いてみることをおすすめします。
他の人の作品を見て学ぶ方法(「中を見る」機能)
Scratchの素晴らしい点の1つは、世界中の人が作った作品を見て、そのプログラムを研究できることです。
Scratchのトップページで「見る」というメニューをクリックすると、たくさんの作品が表示されます。気になる作品を見つけたら、その作品ページの「中を見る」というボタンをクリックしてください。
すると、その作品がどんなブロックで作られているのか、すべて見ることができます。これは、料理に例えれば「レシピを公開してくれている」ようなものです。
「このキャラクターはどうやって動いているんだろう?」「この音はどうやって鳴らしているんだろう?」という疑問を、実際のプログラムを見ながら学ぶことができます。
おすすめの学び方:
- 自分が面白いと思った作品を見つける
- 「中を見る」をクリックして、プログラムを見る
- 気になるブロックの組み合わせをメモする
- 自分の作品で同じ技を試してみる
Scratch3.0対応の書籍を選ぶ注意点
本を使って体系的に学びたい場合は、書籍を1冊購入するのもおすすめです。本には、基礎から応用まで、順を追って学べるプロジェクトが複数掲載されていることが多いです。
ただし、必ず「Scratch3.0対応」と書かれた本を選んでください。
Scratchは2019年1月にバージョン2からバージョン3に大幅にアップデートされました。古いバージョン(Scratch2.0)向けの本を買ってしまうと、画面の見た目やブロックの配置が違うため、混乱してしまいます。
本を選ぶときは、次の点を確認しましょう:
- 表紙に「Scratch3.0対応」「最新版対応」と書かれているか
- 出版年が2019年以降か(それより古い本はScratch2.0の可能性が高い)
- レビューで「分かりやすい」と評価されているか
✅ 次に試したい学習方法
- NHK「ワイワイプログラミング」で新しいプロジェクトに挑戦する
- 他の人の作品を「中を見る」で研究する
- Scratch3.0対応の書籍を1冊購入して、順番に作ってみる
- 自分でオリジナルのゲームやアニメのアイデアを考えてみる
- 完成した作品を保存して、友達や家族に見せる
Scratchの次のステップは?卒業のタイミング
Scratchは素晴らしいプログラミング教材ですが、いつまでもScratchだけをやり続けることが最善とは限りません。ある程度慣れてきたら、次のステップに進むことも視野に入れましょう。
一通り操作に慣れたら本格的な言語へ
Scratchでループや条件分岐の考え方をしっかり理解できたら、それは「次のステージに進む準備ができた」というサインかもしれません。
次のステップとしては、以下のような選択肢があります:
- Python(パイソン):初心者に優しく、世界中で人気のプログラミング言語。AI(人工知能)やデータ分析にも使われています
- JavaScript(ジャバスクリプト):ウェブサイトを動かすための言語。自分のウェブサイトを作りたい人におすすめ
- Unity(ユニティ):本格的な3Dゲームを作るためのツール。将来ゲームクリエイターになりたい人におすすめ
これらの言語では、ブロックではなく「コード」と呼ばれる英語のような命令文を書いてプログラムを作ります。最初は難しく感じるかもしれませんが、Scratchで学んだ考え方がそのまま活きるので、思ったよりスムーズに理解できるはずです。
Scratchで学んだ考え方は全て活きる
Scratchから他の言語に移っても、学んだことは決して無駄にはなりません。むしろ、Scratchで身につけた考え方は、どんなプログラミング言語でも共通する「土台」になります。
例えば:
- Scratchの「ずっと」→ Pythonでは「while」や「for」という命令で同じことができる
- Scratchの「もし〜なら」→ Pythonでは「if」という命令で同じことができる
- Scratchの「🚩 が押されたとき」→ Pythonでは「関数」や「イベントハンドラ」という仕組みで同じことができる
言語が変わっても、「繰り返し」「条件分岐」「イベント処理」という考え方は同じです。Scratchで土台を作ったからこそ、次のステップにスムーズに進めます。
年齢別おすすめの次のステップ
お子さんの年齢や興味に応じて、次のステップを選んでみてください:
- 小学3〜4年生:まだScratchをもっと極める。複雑なゲームやアニメーション作りに挑戦
- 小学5〜6年生:簡単なコードを書き始める。Pythonの入門書やオンライン学習サイトを試してみる
- 中学生以上:本格的なプログラミング言語(Python、JavaScript)を学ぶ。ウェブサイト作りやアプリ開発に挑戦
ただし、これはあくまで目安です。お子さんの興味やペースに合わせて進めることが最も重要です。「まだScratchが楽しい!」と感じているなら、無理に次に進む必要はありません。
🎓 Scratchは「プログラミング小学校」
Scratchは、プログラミングの世界における「小学校」のようなものです。ここで基礎をしっかり学んだら、次は「中学校」(Python、JavaScriptなど)に進学します。
小学校で学んだ「読み書き計算」が、中学・高校・大学でも役立つように、Scratchで学んだ「ループ・条件分岐・イベント処理」は、どんなプログラミングの世界でも役立ちます。
焦らず、楽しみながら、一歩ずつ進んでいきましょう。
次のステップに進む前に:タイピングスキルを身につけよう
Scratchの次にPythonやJavaScriptといった本格的なプログラミング言語を学ぶ場合、タイピングスキル(キーボードを打つ速さと正確さ)が重要になってきます。
ブロックを組み合わせるScratchと違い、これらの言語では英語のコードを自分で打ち込む必要があります。タイピングが遅いと、プログラミングの学習効率が大きく下がってしまいます。
楽しくタイピングを学べる「コード打」
プログラミングを続けるなら、早いうちからタイピングの練習を始めることをおすすめします。特に、プログラミング専用のタイピング練習ツール「コード打」は、実際のコードを打ちながらタイピングが学べるので、一石二鳥です。
👉 詳しくはこちら:【無料】プログラミングが学べるタイピングゲーム「コード打」で楽しくコーディング力UP!
⌨️ タイピングはプログラミングの「ペン」
タイピングは、プログラマーにとって「ペン」のようなものです。どんなに素晴らしいアイデアがあっても、それを形にする道具(タイピング)がないと、思い通りに作れません。
Scratchを楽しんでいる間に、少しずつタイピングも練習しておくと、次のステップへの移行がスムーズになります。
まとめ:Scratchでプログラミングの第一歩を踏み出そう
この記事では、Scratch(スクラッチ)の基本的な使い方から、簡単なゲーム作りまでを解説しました。最後に、重要なポイントをおさらいしましょう。
- Scratchはプログラミングの入り口として最適:無料で、キーボード入力不要で、楽しく学べる
- ブロックを組み合わせるだけで本格的な考え方が学べる:ループ処理、条件分岐、イベント処理という3つの重要概念をマスター
- まずは簡単なゲームを完成させることが大切:小さな成功体験が、次の学びへのモチベーションになる
- NHKサイトや他の人の作品を見ながら学習を継続しよう:独学でも学べる環境が整っている
- 慣れてきたら次のステップへ:Python、JavaScriptなど本格的な言語に挑戦してみよう
プログラミングは、一度にすべてを理解する必要はありません。少しずつ、楽しみながら進めていくことが、長続きの秘訣です。
お子さんが「できた!」という達成感を感じられるよう、保護者の方も一緒に楽しんでサポートしてあげてください。この記事が、お子さんのプログラミング学習の第一歩の助けになれば幸いです。
関連記事:お子さんの年齢に合わせて選ぼう
👶 未就学児〜小学2年生向け
超かんたん体験コース
もっと小さなお子さんには、さらに簡単な「体験重視」の記事がおすすめです。保護者と一緒に、初めてのプログラミングを楽しく体験できます。
🎮 小学3〜6年生向け
ステップアップ実践コース
この記事は、ループや条件分岐といったプログラミングの考え方を学びながら、実際にゲームを完成させる内容です。お子さんが主体的に取り組めるレベルです。
(今ご覧いただいている記事です)
お子さんの年齢や経験に合わせて、最適な記事を選んでください。どちらの記事も、プログラミングの楽しさを伝えることを大切にしています。
参考・出典
- 動画タイトル:はじめてのScratchプログラミング入門|スクラッチの基本と使い方【小学生でも出来る!Scratchでゲームやプログラミング】
チャンネル名:せお丸@AI駆動開発協会
URL:https://www.youtube.com/watch?v=awf_cM1UJLk - Scratch公式サイト:https://scratch.mit.edu/
- NHK ワイワイ プログラミング:https://www.nhk.or.jp/school/programming/