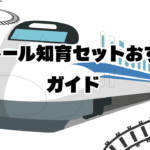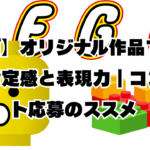不登校・発達障害の中学生向け|高校進学5つの選択肢と進路設計の完全ガイド
- 公開日:2025/11/7
- 最終更新日:
- 特性別ガイド
- 不登校・発達障害の中学生向け|高校進学5つの選択肢と進路設計の完全ガイド はコメントを受け付けていません
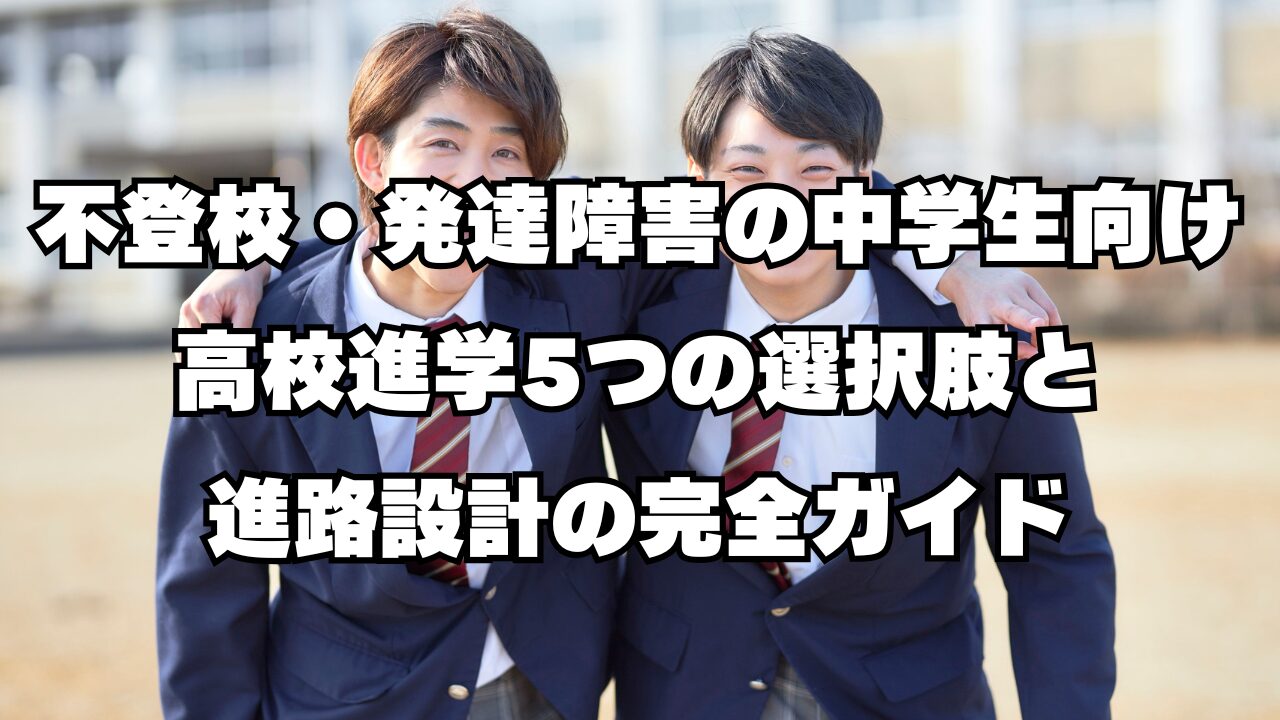
「中学で不登校だったけど、高校には行けるだろうか?」「発達障害のある子に合う高校は?」「全日制以外の選択肢ってあるの?」
こうした不安を抱える生徒・保護者の方は少なくありません。でも、安心してください。高校進学の選択肢は、実は驚くほど多様化しています。
この記事では、不登校経験者・発達障害のある生徒が利用できる5つの高校進学の選択肢について、文部科学省の最新データに基づき詳しく解説します。さらに、高校卒業後の大学進学・就職支援まで含めた「進路設計の全体像」をお伝えします。
💡 高校進学は「橋の架け替え」
中学までの不登校は、古い橋が使えなくなった状態です。高校進学は、同じ場所に新しい橋を架け直すのではなく、別のルートに新しい橋を架ける作業に似ています。全日制という「大きな吊り橋」だけでなく、通信制という「小さな歩道橋」、定時制という「ゆっくり渡れる橋」など、複数の選択肢があります。大切なのは、自分に合った橋を選ぶことです。
この記事を読めば、あなたやお子さんに合った高校の選び方、進路設計の方法がわかります。専門知識は不要です!
注:高校進学の方法は様々です。この記事では不登校・発達障害のある生徒向けの主要な選択肢に焦点を当てていますが、地域や個別の状況により他の選択肢もあります。
⚠️ 重要な方針転換(2019年10月 文部科学省通知)
文部科学省は通知において、「学校復帰のみを目標とするのではなく、児童生徒が自らの進路を主体的に捉えて、社会的に自立することを目指す」と明記しています。つまり、「元の中学校に戻ること」だけが目標ではなく、一人ひとりに合った進路を選ぶことが重視されているのです。
不登校生徒の高校進学:最新状況
不登校でも高校に進学できる
文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」(令和5年度)によれば、中学3年生で不登校だった生徒のうち、約85%が高校等に進学しています。
つまり、不登校経験があっても、多くの生徒が高校進学を果たしているのです。「不登校だったから高校には行けない」というのは誤解です。不登校の最新統計データからも、多様な進路選択が進んでいることがわかります。
進学先の内訳(概算)
- 全日制高校:約40%
- 通信制高校:約30%(近年増加傾向)
- 定時制高校:約10%
- 高等専修学校:約5%
- その他(就職・高卒認定試験準備等):約15%
※文部科学省調査および各種統計から推定した概算値です。
💡 高校選びは「移動手段の選択」
目的地(高校卒業・社会的自立)に向かう手段は一つではありません。全日制は「定期バス」、決まった時刻に毎日運行します。通信制は「レンタカー」、自分の都合で動けます。定時制は「夜行バス」、時間帯を選べます。高卒認定試験は「徒歩」、自分の足で進みます。どれも目的地に着けますが、自分に合った手段を選ぶことが大切です。
高校の種類と特徴:5つの選択肢
高校進学には、大きく分けて以下の5つの選択肢があります。それぞれの特徴を理解し、発達障害の特性に合わせた選択をすることが重要です。
全日制高校
登校頻度:週5日
授業時間帯:昼間
向いている生徒:毎日通学できる生徒
通信制高校
登校頻度:月1~週数日(学校により異なる)
授業時間帯:スクーリング時のみ
向いている生徒:自分のペースで学びたい生徒
定時制高校
登校頻度:週5日程度
授業時間帯:夜間・昼間・午前など
向いている生徒:働きながら学びたい、少人数が良い生徒
高等専修学校
登校頻度:週5日程度
授業時間帯:昼間
向いている生徒:専門技術を学びたい生徒
高卒認定試験
登校:なし(独学)
試験:年2回(8月・11月)
向いている生徒:高校に通わず資格を得たい生徒
すべて「高校卒業資格」または「高校卒業と同等の資格」が得られます。
通信制高校:柔軟な学びの仕組み
通信制高校とは
通信制高校は、自宅学習を中心に、レポート提出・スクーリング(面接指導)・試験により単位を取得する高校です。全日制と同じ「高校卒業資格」が得られます。
通信制高校の特徴
- 登校頻度が少ない:学校により月1~2回から週数日まで選択可能
- 自分のペースで学習:体調や特性に合わせて学習時間を調整できる
- 多様な学習形態:オンライン授業、動画教材、個別指導など
- 年齢層が幅広い:10代から社会人まで在籍
💡 通信制高校は「温室栽培」
全日制高校が「露地栽培」(自然環境で育つ)だとすれば、通信制高校は「温室栽培」です。温度・湿度・日照時間を個別に調整でき、それぞれの植物(生徒)に最適な環境を整えられます。じっくり時間をかけて、確実に成長することができます。
公立と私立の違い
【公立通信制高校】(都道府県教育委員会設置)
- 学費:年間3~5万円程度(授業料のみ)
- 登校頻度:月1~2回程度のスクーリング
- サポート:基本的に自学自習中心
【私立通信制高校】(学校法人設置)
- 学費:年間20~100万円程度(学校・コースにより大きく異なる、事業者公表値)
- 登校頻度:週1~5日など多様なコース設定
- サポート:個別指導、カウンセリング、進路支援などが充実
通信制高校選びのチェックポイント
- 自分が通える登校頻度のコースがあるか
- 発達障害への理解・配慮があるか
- 就学支援金制度を利用した場合の実質負担額はいくらか
- 学校公表の卒業率は何%か
- 大学進学・就職のサポート体制はあるか
情報入手先(公的機関・無料):都道府県教育委員会のウェブサイト、各学校の説明会・見学会
定時制高校:自分のペースで学ぶ
定時制高校とは
定時制高校は、夜間や昼間の特定の時間帯に授業を行う高校です。働きながら学ぶ生徒や、全日制では通学が難しい生徒が多く在籍しています。
定時制高校の特徴
- 多様な時間帯:夜間部・昼間部・午前部など(学校により異なる)
- 少人数クラス:1クラス10~20人程度が一般的
- 4年制が基本:ただし3年で卒業できる制度もあり
- 学費が安い:公立の場合、年間3~5万円程度
定時制高校が向いている生徒
- 毎日の通学は可能だが、朝が苦手
- 少人数の落ち着いた環境で学びたい
- アルバイトをしながら学びたい
- 全日制より時間をかけてゆっくり学びたい
全国の公立定時制高校は約650校(文部科学省「学校基本調査」令和5年度)。都道府県教育委員会のウェブサイトで情報を確認できます。
高等専修学校:専門技術と高卒資格
高等専修学校とは
高等専修学校は、専門的な技術・知識を学びながら、高校卒業資格も取得できる学校です(大学入学資格付与指定校の場合)。調理、美容、IT、福祉、音楽、デザインなど、多様な分野があります。
高等専修学校の特徴
- 実践的な学び:座学より実習・実技が多い
- 少人数教育:1クラス15~25人程度が一般的
- 高卒資格:「大学入学資格付与指定校」では、卒業時に高校卒業と同等の資格を取得可能
- 就職に直結:専門技能を活かした就職が可能
💡 高等専修学校は「職人の工房」
高等専修学校は、「職人の工房」で弟子入り修行をするイメージです。普通科高校が「総合書店」(幅広く学ぶ)だとすれば、高等専修学校は「専門店」(特定分野を深く学ぶ)。調理なら包丁の握り方から、ITならプログラミングの基礎から、実際に手を動かして技術を身につけます。
高等専修学校が向いている生徒
- 興味のある専門分野がある
- 座学より実習・実技が得意
- 将来の職業を具体的にイメージしている
- 手に職をつけたい
情報入手先:全国専修学校各種学校総連合会、都道府県の専修学校協会、各学校のウェブサイト。ハローワークの専門支援と連携することで、卒業後の就職もスムーズになります。
高卒認定試験:高校に通わない選択肢
高卒認定試験とは
高等学校卒業程度認定試験(高卒認定試験)は、高校を卒業していない人が、高校卒業者と同等以上の学力があることを認定する国の試験です。合格すれば、大学・短大・専門学校の受験資格を得られます。
高卒認定試験の基本情報
- 受験資格:16歳以上(試験日の属する年度末までに満16歳以上になる者)
- 試験科目:8~10科目(最大10科目、一部免除あり)
- 試験時期:年2回(8月・11月)
- 受験料:科目数により4,500円~8,500円
- 合格率:約40%(全科目合格者の割合、文部科学省公表値)
💡 高卒認定試験は「運転免許試験」
高卒認定試験は、「自動車運転免許試験」に似ています。教習所(高校)に通わなくても、独学で勉強し、試験に合格すれば免許(資格)が得られます。ただし、教習所では運転技術だけでなく、仲間との交流や教官からの指導も受けられます。高卒認定試験は「資格取得の近道」ですが、「高校生活の経験」は得られません。
⚠️ 高卒認定試験の注意点
「高校卒業」とは異なる:高卒認定試験合格は「高校卒業と同等の学力」を証明するもので、「高校卒業」ではありません。一部の企業・公務員試験では「高校卒業」が応募条件の場合があります。
独学が基本:学校のようなサポートはないため、自己管理能力が求められます。民間の高卒認定試験対策講座(有料)を利用する方法もあります。
情報入手先(公的機関・無料):文部科学省 高等学校卒業程度認定試験、都道府県教育委員会
発達障害のある生徒への合理的配慮
合理的配慮とは
合理的配慮とは、障害者差別解消法に基づき、障害のある人が他の人と同じように権利を行使できるよう、個別に必要な配慮を行うことです。高校でも、発達障害のある生徒に対して合理的配慮が提供されます。
高校で受けられる合理的配慮の例
【ASD(自閉スペクトラム症)】
- 座席位置の配慮(刺激の少ない場所)
- 視覚的な指示(スケジュール表、手順書)
- 静かな環境での試験実施
- 個別の相談室・クールダウンスペースの提供
【ADHD(注意欠如・多動症)】
- 指示の明確化・簡潔化
- タイマーやリマインダーの使用許可
- 動きを取り入れた学習(立ち歩きの許可など)
- 提出期限の柔軟な設定
【LD(学習障害)】
- 試験時間の延長
- 読み書きの補助(タブレット・音声読み上げソフト)
- 問題文の拡大・色分け
- 別室での試験実施
合理的配慮は、「特別扱い」ではなく、法律で保障された権利です。遠慮せず、必要な配慮を学校に伝えましょう。私立学校も、障害者差別解消法により合理的配慮の提供が義務付けられています(令和6年4月~)。発達障害者支援センターや教育支援センターでも相談できます。
高校卒業後の進路:大学・就職・支援
高校卒業後の4つの進路
1. 大学・短大進学
- 一般入試、総合型選抜(旧AO入試)、学校推薦型選抜
- 一部の大学では障害者特別選抜を実施
- 大学でも合理的配慮が提供される(各大学の「学生支援室」に相談)
2. 専門学校進学
- 専門技術・資格取得を目指す
- 実習・実技中心のカリキュラム
3. 就職
- 一般就労または障害者雇用枠
- ハローワーク専門支援(障害学生等雇用サポーター、精神・発達障害者雇用サポーター)
4. 就労移行支援・職業訓練
- 就労移行支援事業所(原則2年間、障害福祉サービス)
- 職業訓練校(公共職業訓練、ハローワーク経由)
💡 進路選択は「旅行プランニング」
高校卒業後の進路選択は、「旅行のプランニング」に似ています。大学進学は「長期旅行」、専門学校は「短期集中ツアー」、就職は「移住」、就労移行支援は「下見ツアー」。どのプランも目的地(社会的自立)に向かいますが、かかる時間・費用・経験が異なります。自分に合ったプランを選びましょう。
進路選択のステップとチェックリスト
進路選択の5ステップ
学校選びのチェックポイント
- 自分が通える登校頻度のコースがあるか
- 通学時間は無理なく通える距離か
- 特別支援コーディネーター、カウンセラーがいるか
- 自分に必要な合理的配慮が受けられるか
- 家庭で負担できる学費か(就学支援金制度の利用含む)
- 学校公表の卒業率は何%か
- 大学進学・就職のサポートはあるか
- 見学して、居心地が良いと感じたか
- 本人が「ここに通いたい」と思っているか
相談先(公的機関・無料):都道府県教育委員会、発達障害者支援センター、教育支援センター、中学校の特別支援コーディネーター
よくある質問(FAQ)
中学で不登校でしたが、高校入試は受けられますか?
はい、受けられます。多くの都道府県では、不登校の生徒に配慮した入試制度があります。例えば、調査書の欠席日数を選考資料としない「自己推薦入試」や、面接・作文を重視する選抜などです。都道府県教育委員会や中学校の進路指導担当に確認してください。出席扱い制度を活用している場合は、その記録も活用できます。
通信制高校は「恥ずかしい」と思われますか?
いいえ。通信制高校は、全日制と同じ「高校卒業資格」が得られる正式な高校です。近年、通信制高校の在籍者数は増加しており(約21万人、文部科学省「学校基本調査」令和5年度)、社会的な認知も高まっています。大切なのは、自分に合った環境で学び、卒業することです。
発達障害があることを学校に伝えるべきですか?
伝えることを強くおすすめします。合理的配慮を受けるには、学校が発達障害について把握している必要があります。診断書や中学校での支援記録を提示することで、適切なサポートを受けやすくなります。情報は、必要な教職員のみで共有され、プライバシーは守られます。ペアレントプログラムで学んだ支援方法を学校と共有することも有効です。
高卒認定試験に合格すれば、高校卒業と同じ扱いになりますか?
「大学・専門学校の受験資格」については同じ扱いですが、「高校卒業」とは異なります。一部の企業・公務員試験では、応募資格が「高校卒業」と明記されている場合があり、高卒認定試験合格では応募できないことがあります。
全日制高校から通信制高校への転校は可能ですか?
はい、可能です。「転入」(在学中の転校)と「編入」(退学後の再入学)があり、取得済みの単位は多くの場合引き継がれます。ただし、学校により受け入れ時期や条件が異なるため、希望する通信制高校に早めに相談してください。フリースクールを併用しながら通信制高校に在籍する選択肢もあります。
通信制高校の学費は、就学支援金制度で軽減できますか?
はい、できます。高等学校等就学支援金制度により、所得要件を満たせば、授業料の一部または全額が支給されます。公立通信制高校では、実質無償になる場合が多いです。私立通信制高校でも、年間約30万円まで支給される場合があります(世帯所得により異なる)。詳細は、各学校または都道府県の担当窓口に確認してください。
まとめ:自分に合った進路を見つけよう
高校進学の選択肢は、驚くほど多様です。この記事では、不登校経験者・発達障害のある生徒向けの高校進学について解説しました:
- 不登校生徒の約85%が高校等に進学している(文部科学省データ)
不登校経験があっても、多くの生徒が高校進学を果たしています。
- 5つの選択肢:全日制・通信制・定時制高校、高等専修学校、高卒認定試験
それぞれに特徴があり、自分に合った道を選べます。
- 通信制高校:自分のペースで学べる(公立・私立あり)
公立は学費が安く、私立はサポートが充実しています。
- 合理的配慮は権利:遠慮せず学校に伝える
発達障害のある生徒には、法律で保障された配慮が提供されます。
- 高校卒業後も多様な進路:大学・就職・支援制度
高校卒業後も、様々な選択肢があります。
大切なのは、「どの高校が正解か」ではなく、「自分に合った環境で学べるか」です。文部科学省も、「学校復帰のみを目標とするのではなく、社会的自立を目指す」としています。
焦らず、自分のペースで、自分に合った道を選んでください。次のステップは、都道府県教育委員会のウェブサイトで高校一覧を確認すること、気になる学校の説明会に参加することです。
進路選択は、ゴールではなくスタートです。高校生活を通じて、自分らしい生き方を見つけていきましょう。発達障害・不登校支援の完全ガイドでは、教育から就労まで一貫した支援の流れを詳しく解説しています。