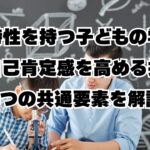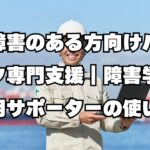発達特性を持つ子どもの学習意欲と自己肯定感を高める指導法|4つの共通要素を解説 「発達特性を持つ子どもが、なかなか学習に意欲を示さない」「自信を持てず、すぐに諦めてしまう」——こうした悩みを抱えている教育関係者や保護者の方は少なくありません。 この記事では、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注…
フリースクールと教育支援センターの違い|費用・出席扱い・活動内容を徹底比較
- 公開日:2025/11/7
- 最終更新日:
- 特性別ガイド
- フリースクールと教育支援センターの違い|費用・出席扱い・活動内容を徹底比較 はコメントを受け付けていません
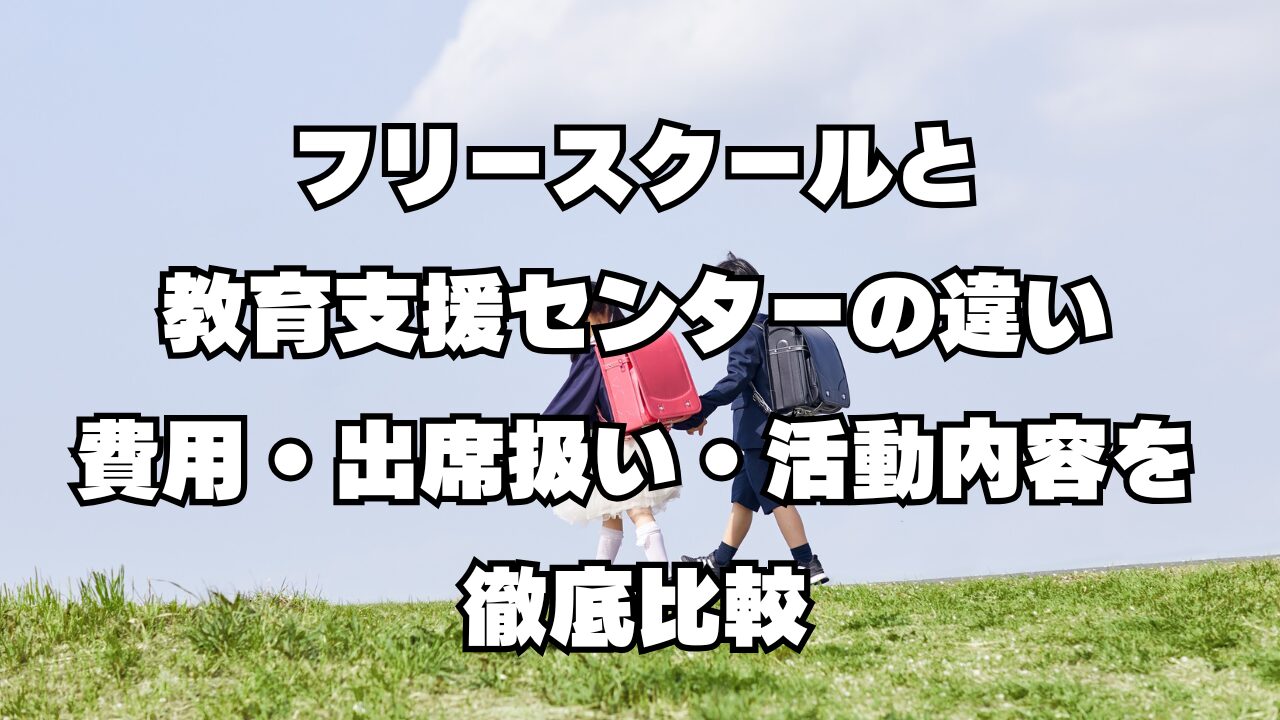
「不登校の子どもに居場所を作ってあげたい」「フリースクールと適応指導教室って何が違うの?」「どっちがうちの子に合っているの?」
こうした疑問を持つ保護者の方は少なくありません。実は、フリースクール(民間施設)と教育支援センター(適応指導教室・公的機関)は、設置主体、費用、活動内容が大きく異なります。
この記事では、フリースクールと教育支援センターの違いについて、費用、出席扱い、活動内容、メリット・デメリットを詳しく比較し、お子さんに合った選び方を解説します。
💡 フリースクールと教育支援センターは「私立病院と公立病院」
両者の違いは、「私立病院と公立病院」に例えられます。公立病院(教育支援センター)は、自治体が運営し、費用は無料または低額です。私立病院(フリースクール)は、民間が運営し、費用は高めですが、独自のプログラムやきめ細やかなサービスがあります。どちらも「治療」(支援)を提供しますが、運営主体、費用、サービス内容が異なります。自分に合った病院を選ぶように、子どもに合った居場所を選ぶことが大切です。
この記事を読めば、両者の違い、選び方のポイント、併用の可能性がわかります。専門知識は不要です!
注:不登校の居場所は、フリースクールと教育支援センター以外にも、学校内の別室登校、オンライン学習、家庭での学習など多様な選択肢があります。この記事では主要な2つに焦点を当てています。
教育支援センター(適応指導教室)とは
教育支援センターの基本情報
教育支援センター(旧称:適応指導教室)は、教育委員会が設置・運営する不登校児童生徒の支援施設です。
- 設置主体:市区町村教育委員会(公的機関)
- 設置数:全国約1,700箇所
- 通所者数:約26,000人(令和5年度、文部科学省調査)
- 費用:無料
- 対象:不登校の小中学生(主に在籍校の教育委員会管轄内の児童生徒)
教育支援センターの目的
文部科学省の通知では、教育支援センターの目的を以下のように定めています。
- 学校復帰の支援:学校に戻るための準備と支援
- 社会的自立の支援:学校復帰だけでなく、社会的自立も目指す
- 学習支援:基礎学力の維持・向上
- 心理的支援:安心できる居場所の提供
※ただし、文部科学省は2019年10月の通知で「学校復帰のみを目標とせず、社会的自立を目指す」と方針転換しています。
教育支援センターの活動内容
教育支援センターでは、以下のような活動が行われています(施設により異なります)。
- 個別学習:プリント学習、ドリル、教科書を使った学習
- 集団活動:レクリエーション、調理実習、工作、スポーツなど
- 相談・カウンセリング:教員やカウンセラーとの面談
- 体験活動:校外学習、職場体験、ボランティア活動など
出席扱いについて
教育支援センターに通所した場合、原則として在籍校の出席扱いになります(文部科学省通知に基づく)。これは、高校進学の際の内申書に有利に働く可能性があります。
フリースクールとは
フリースクールの基本情報
フリースクールは、民間団体やNPO法人が運営する不登校児童生徒の居場所・学びの場です。
- 設置主体:民間団体、NPO法人、株式会社など(民間事業者)
- 施設数:全国約500箇所(推定、正確な統計なし)
- 通所者数:約20,000人(推定)
- 費用:月額3~5万円程度(事業者公表値、施設により大きく異なる)
- 対象:不登校の小中学生、高校生(施設により異なる)
フリースクールの目的
フリースクールは、施設により理念や目的が異なりますが、一般的に以下を目指しています。
- 安心できる居場所の提供:学校以外の安全な場所
- 個性の尊重:一人ひとりの個性や興味を大切にする
- 自主性の育成:子ども自身が学びたいことを選ぶ
- 社会性の獲得:仲間との交流を通じた成長
フリースクールの活動内容
フリースクールの活動は、施設により大きく異なります。代表的な活動例は以下の通りです。
- 自由な学習:子ども自身が学びたいことを選ぶ
- 体験活動:アート、音楽、農業、料理、自然体験など
- 集団活動:ゲーム、スポーツ、遠足、キャンプなど
- 個別サポート:スタッフとの1対1の対話
- オンライン活動:オンラインでの交流や学習(一部施設)
💡 フリースクールの多様性は「レストランのバリエーション」
フリースクールの多様性は、「レストランのバリエーション」に似ています。和食、洋食、中華、エスニックなど、レストランにはさまざまな種類があります。フリースクールも同じで、学習重視型、体験活動型、デモクラティックスクール型など、施設により理念や活動内容が大きく異なります。レストラン選びと同じように、子どもの好みや特性に合った施設を選ぶことが大切です。
出席扱いについて
フリースクールへの通所が出席扱いになるかどうかは、在籍校の校長の判断によります(文部科学省通知)。
出席扱いが認められる場合もあれば、認められない場合もあります。事前に学校に確認することが重要です。詳しくは出席扱い制度の7要件をご覧ください。
フリースクールと教育支援センターの比較
主要な違いの一覧
教育支援センター
設置主体:市区町村教育委員会(公的機関)
費用:無料
出席扱い:原則として認められる
活動内容:学習中心、学校復帰を視野に入れた支援
スタッフ:教員、教育相談員、心理士など
フリースクール
設置主体:民間団体、NPO、株式会社(民間事業者)
費用:月額3~5万円程度(事業者公表値)
出席扱い:校長判断(認められる場合とそうでない場合がある)
活動内容:自由度が高い、施設により多様
スタッフ:専門性は施設により異なる
費用の詳細比較
【教育支援センター(公的機関・無料)】
- 通所費用:無料
- 教材費:無料または実費(数百円程度)
- 給食費:施設により異なる(提供がない場合も)
- その他:校外学習の交通費などは実費の場合あり
【フリースクール(民間事業者・有料)】
- 入会金:1~5万円程度(事業者公表値)
- 月額利用料:3~5万円程度(事業者公表値、週5日通所の場合)
- 教材費・活動費:別途必要な場合あり
- 給食・昼食:別途必要または持参
- その他:イベント参加費、交通費など
※週数回の利用など、通所頻度により費用が異なる場合があります。
💡 費用の違いは「公園と遊園地」
費用の違いは、「公園と遊園地」に例えられます。公園(教育支援センター)は、自治体が管理し、誰でも無料で利用できます。基本的な遊具はありますが、種類は限られています。遊園地(フリースクール)は、入場料が必要ですが、多様なアトラクションや独自の体験ができます。どちらも子どもが楽しめる場所ですが、費用とサービス内容が異なります。
活動内容の比較
【教育支援センター】
- 学習重視:国語、算数・数学、英語などの教科学習が中心
- 学校復帰を視野:学校のペースに合わせた学習が多い
- 集団活動:レクリエーション、調理実習、スポーツなど
- 個別対応:教育相談員やカウンセラーとの面談
【フリースクール】
- 自由度が高い:子ども自身が活動を選べる場合が多い
- 多様な体験:アート、音楽、農業、自然体験など
- 個性の尊重:一人ひとりのペースや興味を大切にする
- 学習サポート:施設により学習支援の有無や内容が異なる
出席扱いの違い
【教育支援センター】
教育委員会が設置する公的施設のため、原則として在籍校の出席扱いになります。文部科学省の通知に基づき、多くの学校で認められています。
【フリースクール】
民間施設のため、出席扱いになるかどうかは在籍校の校長の判断によります。
文部科学省の通知(平成4年、平成28年)では、以下の要件を満たす場合、フリースクールでの活動を出席扱いにできるとしています。
- 保護者と学校との間に十分な連携・協力関係があること
- 民間施設への通所が児童生徒の社会的自立を助けると判断されること
- 民間施設での活動状況を学校が把握していること
ただし、校長が認めない場合は出席扱いになりません。事前に学校に確認することが重要です。詳しくは出席扱い制度の7要件をご覧ください。
メリットとデメリットの比較
教育支援センターのメリット・デメリット
【メリット】
- 無料で利用できる:経済的負担がない
- 出席扱いが認められやすい:高校進学に有利
- 公的機関の安心感:教育委員会が運営
- 学校との連携:在籍校と情報共有がスムーズ
- 学習支援が充実:教科学習のサポートがある
【デメリット】
- 場所が限られる:自治体に1~数箇所程度
- 通所に時間がかかる:遠方の場合、通所が負担
- 活動内容が限定的:学校に近い雰囲気の場合がある
- 利用時間が限られる:平日の日中のみ(夕方や土日は利用できない場合が多い)
- 人数が多い:個別対応が難しい場合がある
フリースクールのメリット・デメリット
【メリット】
- 多様な活動:子どもの興味に合わせた体験ができる
- 個性の尊重:一人ひとりのペースや特性を大切にする
- アットホームな雰囲気:少人数で家庭的な環境
- 柔軟な対応:時間や活動内容の融通が利く場合がある
- 専門的なプログラム:発達障害への理解が深い施設もある
【デメリット】
- 費用が高い:月額3~5万円程度の負担(事業者公表値)
- 出席扱いが保証されない:校長の判断による
- 施設により差が大きい:質や内容にバラつきがある
- 学習サポートが不十分:施設により学習支援が弱い場合がある
- 認知度が低い:高校進学時に理解されない可能性がある
💡 メリット・デメリットは「賃貸と持ち家」
教育支援センターとフリースクールのメリット・デメリットは、「賃貸と持ち家」に似ています。賃貸(教育支援センター)は、初期費用が安く、気軽に始められますが、自由度は限られます。持ち家(フリースクール)は、初期費用が高く、維持費もかかりますが、自分好みにカスタマイズできます。どちらが良いかは、家庭の状況と子どもの特性によります。
どちらを選ぶべきか:選び方のポイント
子どもの状況別おすすめ
教育支援センターが向いている子ども
- 学校復帰を目指している
- 学習の遅れを取り戻したい
- 高校進学で出席扱いが必要
- 費用を抑えたい
- 公的機関の安心感を求める
フリースクールが向いている子ども
- 学校の雰囲気が苦手
- 自分のペースで活動したい
- 興味のある体験活動をしたい
- 少人数の環境が合っている
- 発達障害への専門的な理解が必要
選び方のステップ
見学・体験で確認すべきポイント
- 子どもが「行きたい」と感じるか
- スタッフの対応は丁寧か、子どもに寄り添っているか
- 活動内容は子どもの興味に合っているか
- 他の子どもたちの雰囲気はどうか
- 通所の時間・頻度は無理なく続けられるか
- 学習サポートは十分か(必要な場合)
- 費用は家庭で負担できる範囲か(フリースクールの場合)
ペアレント支援プログラムでは、お子様に最適な支援環境の選び方についても学べます。
併用という選択肢
教育支援センターとフリースクールは、必ずしも「どちらか一方」を選ぶ必要はありません。以下のような併用も可能です。
- 週3日は教育支援センター、週2日はフリースクール
- 午前は教育支援センター、午後はフリースクール
- 学習は教育支援センター、体験活動はフリースクール
ただし、併用する場合は、学校と両施設に事前に相談し、出席扱いの取り扱いを確認してください。また、オンライン学習との併用も検討できます。
フリースクール選びの注意点
フリースクールの質の見極め方
フリースクールは民間事業者が運営しているため、施設により質に大きな差があります。以下のポイントを確認してください。
フリースクール選びのチェックポイント
- 運営団体の理念や実績を確認する
- スタッフの資格や経験を確認する(教員免許、心理士資格など)
- 実際に見学・体験をする(雰囲気を確認)
- 在籍している子どもや保護者の声を聞く
- 費用の内訳を明確に確認する(追加費用の有無)
- 退会時の手続きや返金規定を確認する
- 学校との連携状況を確認する(出席扱いの実績など)
⚠️ トラブルを避けるために
フリースクールは、公的な認可や監督がない場合が多く、施設により対応やサービスに大きな差があります。入会前に必ず見学・体験をし、契約内容を十分に確認してください。不明な点があれば、遠慮せず質問しましょう。また、高額な入会金を要求される場合や、退会が難しい規定がある場合は慎重に検討してください。
全国のフリースクール情報
フリースクールの情報は、以下で探すことができます。
- NPO法人フリースクール全国ネットワーク:全国のフリースクール情報を掲載
- 都道府県・市区町村の教育委員会:地域のフリースクール情報を持っている場合がある
- インターネット検索:「フリースクール [地域名]」で検索
教育支援センターの利用方法
利用までの流れ
教育支援センターへの問い合わせ先
- 市区町村教育委員会:教育支援センターの所在地、連絡先を確認
- 在籍校の担任・教頭:学校経由で申し込む場合が多い
※自治体により、利用方法や条件が異なる場合があります。まずは教育委員会または在籍校に確認してください。詳しくは教育支援センターの使い方の記事もご覧ください。
よくある質問(FAQ)
教育支援センターとフリースクール、両方通うことはできますか?
はい、可能な場合があります。ただし、学校と両施設に事前に相談し、通所スケジュールや出席扱いの取り扱いを確認する必要があります。併用する場合、費用(フリースクール分)や通所の負担も考慮してください。
フリースクールに通っても高校に進学できますか?
はい、できます。不登校経験者の約85%が高校等に進学しています。ただし、出席扱いが認められない場合、内申書の欠席日数が多くなる可能性があります。通信制高校、定時制高校、高卒認定試験など、多様な進学ルートを検討してください。
教育支援センターに通うと、必ず学校に戻らなければなりませんか?
いいえ、そうではありません。文部科学省は2019年10月の通知で「学校復帰のみを目標とせず、社会的自立を目指す」と明記しています。教育支援センターも、学校復帰を強制するのではなく、子ども一人ひとりの状況に応じた支援を行っています。
フリースクールの費用は補助されますか?
一部の自治体では、フリースクールの利用費用の補助制度を設けている場合があります(月額数千円~1万円程度)。お住まいの市区町村の教育委員会に問い合わせてください。ただし、補助制度がない自治体の方が多いのが現状です。
教育支援センターに空きがない場合はどうすればいいですか?
教育支援センターの定員が埋まっている場合、待機リストに登録するか、フリースクールなど他の選択肢を検討してください。また、学校内の別室登校、オンライン学習、家庭での学習なども検討できます。教育委員会に相談し、他の支援策を確認してください。
まとめ:子どもに合った居場所を見つけよう
この記事では、フリースクールと教育支援センターの違いを解説しました:
- 教育支援センター(公的機関・無料):教育委員会設置、全国約1,700箇所
出席扱いが認められやすく、学習支援が充実しています。
- フリースクール(民間事業者・有料):月額3~5万円程度(事業者公表値)
多様な活動、個性の尊重、柔軟な対応が特徴です。
- 出席扱いの違い:教育支援センターは原則認められる、フリースクールは校長判断
高校進学を考える場合、出席扱いの有無は重要です。
- 選び方のポイント:子どもの意見、家庭の経済状況、実際の見学・体験
どちらが「正解」ではなく、子どもに合った選択が大切です。
- 併用も可能:週数日ずつなど、柔軟な利用
学校と施設に相談すれば、併用できる場合があります。
大切なのは、子どもが「安心できる居場所」を持つことです。教育支援センターでもフリースクールでも、子どもが「ここなら行ける」「ここが好き」と思える場所が見つかれば、それが最良の選択です。
まずは、両方の見学・体験をしてみてください。子どもの反応を見て、一緒に決めていきましょう。焦らず、子どものペースで進めることが大切です。
その他の支援については、発達障害者支援センターやオンライン学習、将来的にはハローワークの専門支援もご活用ください。
詳しくは発達障害と不登校の包括的な支援ガイドをご覧ください。