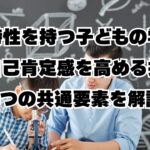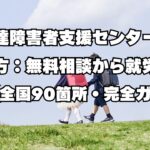発達特性を持つ子どもの学習意欲と自己肯定感を高める指導法|4つの共通要素を解説 「発達特性を持つ子どもが、なかなか学習に意欲を示さない」「自信を持てず、すぐに諦めてしまう」——こうした悩みを抱えている教育関係者や保護者の方は少なくありません。 この記事では、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注…
教育支援センター(適応指導教室)の使い方:無料・出席扱い【全国1,700箇所・完全ガイド】
- 公開日:2025/11/7
- 最終更新日:
- 特性別ガイド
- 教育支援センター(適応指導教室)の使い方:無料・出席扱い【全国1,700箇所・完全ガイド】 はコメントを受け付けていません
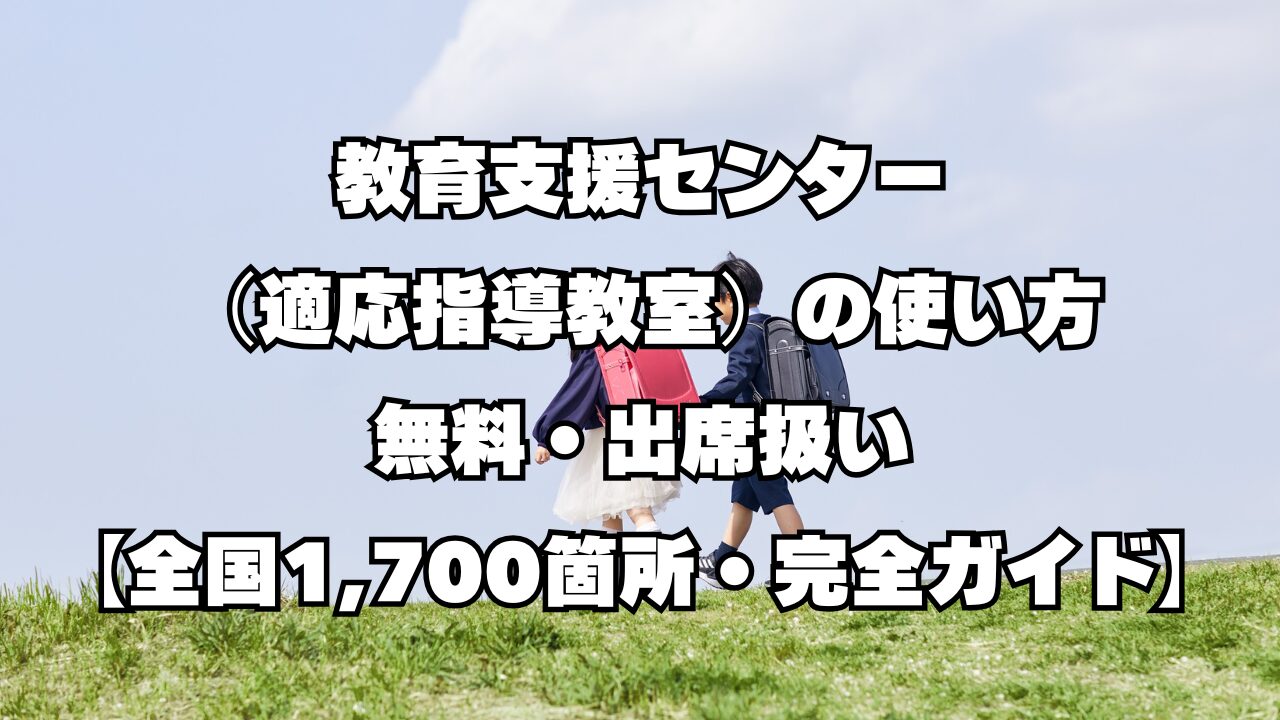
教育支援センター(適応指導教室)の使い方:無料・出席扱い【全国1,700箇所・完全ガイド】
「子どもが学校に行けなくなった…どこに相談すればいいの?」「フリースクールは費用が高くて通えない…」そんな悩みを抱えていませんか?
この記事では、教育支援センター(適応指導教室)の使い方について、フリースクールとの違い、出席扱いの仕組み、利用方法を詳しく解説します。
💡 教育支援センターは「学校とは違う学びの場」
教育支援センターは、メインの道路(学校)とは別の「迂回路」のようなものです。目的地(社会的自立)は同じでも、メインの道が通れないとき、別のルートで進むことができます。景色も違えば、歩くペースも自由。大切なのは、自分に合った道を選んで前に進むことです。
この記事を読めば、教育支援センターで受けられる支援と利用の流れがわかります。(無料で通えて、学校の出席扱いにもなります!)
注:不登校の支援機関は様々です。この記事では教育委員会が設置する「教育支援センター(適応指導教室)」に焦点を当てていますが、他にもフリースクール、オンライン学習、民間の相談機関など多様な選択肢があります。
⚠️ 文部科学省の方針転換(2019年10月)
文部科学省は令和元年(2019年)10月25日の通知で、「学校復帰のみを目標とせず、児童生徒の社会的自立を目指す」という方針を明確にしました。教育支援センターは、学校復帰を強制する場所ではなく、子どもが安心して過ごせる「居場所」と「学びの場」です。
出典:文部科学省「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」令和元年10月25日
教育支援センター(適応指導教室)とは?
教育支援センター(旧称:適応指導教室)は、教育委員会が設置する公的な支援機関です。不登校やその傾向にある児童生徒に対して、学習支援、体験活動、相談等を行い、社会的自立を支援します。
設置主体
教育委員会
都道府県・市区町村の教育委員会が設置・運営
箇所数
全国約1,700箇所
(令和4年度:1,722箇所)
出典:文部科学省「令和4年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」
費用
無料
利用料、相談料はすべて無料
対象となる児童生徒
以下の児童生徒が利用できます:
- 小学生・中学生(義務教育段階)
- 不登校または不登校傾向にある児童生徒
- 在籍校がある児童生徒(学籍は在籍校に残したまま利用)
高校生は対象外のことが多いですが、一部の自治体では高校生向けのプログラムを実施しているところもあります。詳しくはお住まいの教育委員会にお問い合わせください。
💡 学籍は「本籍地」のようなもの
教育支援センターを利用しても、学籍(所属)は元の学校に残ります。これは、住民票の「本籍地」と「現住所」のような関係です。本籍地は変わらないけれど、実際に住んでいる場所は違う。同じように、所属は元の学校のままで、実際に通う場所が教育支援センターになります。卒業証書も、元の学校から授与されます。
フリースクールとの違い
教育支援センターとフリースクールは、どちらも不登校児童生徒の支援機関ですが、大きな違いがあります。
教育支援センター
設置主体:教育委員会(公的機関)
費用:無料
出席扱い:原則として出席扱いになる(在籍校の校長判断)
スタッフ:教員、心理士等の公的職員
活動内容:学習支援、体験活動、相談等
フリースクール
設置主体:民間団体・NPO等
費用:有料(月額3〜5万円程度、事業者公表値)
出席扱い:校長の判断により出席扱いになる場合がある(要件あり)
スタッフ:民間スタッフ
活動内容:施設により多様(学習、体験、自由活動等)
どちらを選ぶべき?
教育支援センターを選ぶと良い場合:
- 費用をかけずに支援を受けたい
- 確実に出席扱いにしたい
- 公的機関のサポートを受けたい
- 将来的に学校復帰を検討している
フリースクールを選ぶと良い場合:
- より自由な雰囲気の場所がいい
- 特定の教育理念に共感している
- 教育支援センターが近くにない、または定員がいっぱい
- 費用を支払える余裕がある
参考記事:フリースクールと教育支援センターの詳しい比較は、記事#7「フリースクールと教育支援センターの違い」をご覧ください。
💡 公立図書館と民間書店の違い
教育支援センターとフリースクールの関係は、公立図書館と民間書店のようなものです。図書館は無料で誰でも利用でき、基本的なサービスが充実しています。一方、書店は有料ですが、カフェ併設や独自のイベントなど、多様なサービスを提供しています。どちらが良いかは、利用者のニーズと予算次第。両方を使い分けることもできます。
出席扱いの仕組み
教育支援センターに通うと、原則として在籍校の出席扱いになります。これは不登校児童生徒にとって大きなメリットです。
出席扱いの根拠
文部科学省は、教育支援センターでの指導について、以下のように通知しています:
「教育支援センターにおける指導等については、在籍校の出欠の取扱いにおいて『出席扱い』とすることができる」
出席扱いの条件
出席扱いになるためには、以下の条件を満たす必要があります:
出席扱いの条件
- 教育委員会が設置する教育支援センターに通っている
- 在籍校の校長が出席扱いと判断する
- 教育支援センターと在籍校が連携している
- 保護者と在籍校が連絡を取り合っている
ほとんどの場合、教育支援センターに通えば自動的に出席扱いになりますが、念のため在籍校の担任または校長に確認しておくことをお勧めします。
通知表や内申書への影響
出席扱いになると、通知表の「出席日数」にカウントされます。ただし、以下の点に注意が必要です:
- 成績評価:教育支援センターでは通常の授業を行わないため、テストを受けていない教科は評価が難しい場合があります。在籍校と相談の上、可能な範囲で評価されます。
- 内申書:高校受験の際、「教育支援センターに通っていた」ことは内申書に記載される場合があります。ただし、これは不利になるものではなく、「支援を受けながら努力した」という評価につながることもあります。
⚠️ 出席扱いは「学校復帰」が目的ではありません
文部科学省の通知(令和元年10月25日)により、出席扱いの目的は「学校復帰」だけではなく、「社会的自立」に変更されました。「学校に戻るため」ではなく、「子どもが安心して学べる場所を確保するため」の制度です。
利用方法と流れ(5ステップ)
教育支援センターの利用は、以下の流れで進みます。
ステップ1: お住まいの教育委員会に問い合わせる
まず、お住まいの市区町村の教育委員会に連絡し、教育支援センターの情報を聞きます。
問い合わせ時に聞くこと
- 教育支援センターの名称と所在地
- 対象学年(小学生・中学生)
- 開所日時(平日の日中が多い)
- 利用方法(申込み手続き)
- 見学や体験の可否
教育委員会の探し方:
- 「○○市 教育委員会」とインターネット検索
- 市区町村の公式ウェブサイトから「教育委員会」のページを探す
- 市役所・区役所の代表電話に問い合わせて教育委員会の電話番号を聞く
参考:文部科学省「教育支援センター(適応指導教室)に関する実態調査」結果(PDF)
ステップ2: 在籍校と相談する
教育支援センターを利用する前に、在籍校(現在通っている学校、または通えなくなった学校)の担任または校長に相談します。
相談内容:
- 「教育支援センターに通いたいと考えています」
- 「出席扱いになりますか?」
- 「学校との連携はどのように行われますか?」
在籍校の協力は必須です。教育支援センターと在籍校が連携することで、出席扱いや学習支援がスムーズに進みます。
💡 在籍校は「主治医」、教育支援センターは「専門医」
在籍校と教育支援センターの関係は、「主治医」と「専門医」のようなものです。主治医(在籍校)が患者(子ども)の状態を把握し、必要に応じて専門医(教育支援センター)を紹介します。専門医の治療内容は主治医に報告され、両者が協力して患者をサポートします。勝手に専門医にかかるのではなく、主治医を通すことで、連携がスムーズになります。
ステップ3: 教育支援センターで面談・見学
教育委員会または在籍校を通じて、教育支援センターでの面談・見学を予約します。
面談の内容:
- 子どもの状況のヒアリング(不登校のきっかけ、現在の様子等)
- 教育支援センターの説明(活動内容、ルール、スケジュール等)
- 施設見学(教室、図書スペース、体育館等)
- 通所の希望日時の相談
多くのセンターでは、子ども本人も一緒に見学することを推奨しています。雰囲気を実際に見て、「ここなら通えそう」と感じることが大切です。
見学時に確認すると良いこと
- どんな子どもたちが通っているか(年齢層、人数)
- スタッフの雰囲気(優しそうか、話しやすそうか)
- 活動内容(学習、体験、自由時間等)
- 通所頻度(毎日でなくてもいいか)
- 保護者の関わり方(送迎、面談等)
ステップ4: 通所開始(試験的な通所から始めることが多い)
面談・見学後、通所を開始します。多くの場合、最初は週1〜2回の試験的な通所から始め、徐々に頻度を増やしていきます。
通所のパターン例:
- 週1回コース:まずは慣れるために週1回から
- 週2〜3回コース:慣れてきたら週2〜3回に増やす
- 毎日コース:安定したら毎日通う(ただし、無理は禁物)
通所頻度は、子どもの状態や希望に応じて柔軟に調整できます。「毎日通わなければならない」というプレッシャーはありません。
💡 試験的通所は「リハビリ」
教育支援センターへの通所は、怪我の後の「リハビリ」に例えられます。いきなり全力で走るのではなく、最初は歩くことから始めます。少しずつ距離を伸ばし、体が慣れてきたら走る練習をする。同じように、週1回から始めて、徐々に通所日数を増やすことで、無理なく「通う習慣」を取り戻せます。
ステップ5: 定期的な通所と在籍校との連携
通所が安定してきたら、教育支援センターと在籍校が定期的に情報を共有します。
連携の内容:
- 出席日数の報告(月1回程度)
- 子どもの様子の報告(学習状況、対人関係等)
- 必要に応じて三者面談(保護者、在籍校、教育支援センター)
- 学校行事への参加の調整(運動会、卒業式等)
保護者は、在籍校とも定期的に連絡を取り合うことが大切です。
教育支援センターの活動内容
教育支援センターでは、主に以下の3つの活動を行います。
①学習支援
個別または小グループで、学習のサポートを行います。
- 教科学習:国語、算数(数学)、英語等の基礎学習
- 個別対応:一人ひとりの学習進度に合わせた指導
- プリント学習:ドリルやプリントを使った反復学習
- オンライン学習:タブレットやPCを使った学習(一部のセンター)
学校のような一斉授業ではなく、自分のペースで学習できるのが特徴です。
②体験活動
学習以外の様々な体験活動を通じて、社会性やコミュニケーション能力を育みます。
- 創作活動:工作、絵画、音楽等
- スポーツ:体育館での軽い運動、散歩等
- 調理実習:簡単な料理やお菓子作り
- 校外活動:博物館見学、公園での活動等
- グループ活動:ゲーム、ディスカッション等
💡 体験活動は「心の栄養補給」
体験活動は、体に必要な「ビタミン」のようなものです。勉強(主食)だけでは心が疲れてしまいますが、楽しい体験(ビタミン)を取り入れることで、心が元気になります。工作で何かを作る達成感、スポーツで体を動かす爽快感、仲間との会話で感じる安心感。これらが「学ぶ意欲」を取り戻すエネルギーになります。
③相談・カウンセリング
子ども本人や保護者からの相談に応じます。
- 個別相談:心理士やカウンセラーとの定期面談
- 保護者相談:子どもへの接し方、進路の相談等
- 進路相談:高校進学、将来の選択肢等
スタッフは、教員、心理士、社会福祉士等の専門家です。安心して相談できます。
よくある質問
Q1. 毎日通わなければなりませんか?
いいえ。通所頻度は子どもの状態に合わせて調整できます。週1回から始めて、徐々に増やすことも可能です。「毎日通えない」ことを理由に利用を諦める必要はありません。
Q2. 学校に戻らなければなりませんか?
いいえ。文部科学省の方針(令和元年10月通知)により、「学校復帰のみを目標としない」とされています。教育支援センターは、学校復帰を強制する場所ではなく、子どもが安心して過ごせる「居場所」です。
Q3. 他の子どもたちと交流しなければなりませんか?
交流は強制ではありません。最初は一人で過ごし、慣れてきたら少しずつ他の子どもと関わる、というペースでOKです。スタッフが無理のない範囲でサポートします。
Q4. 送迎は必要ですか?
多くの場合、保護者による送迎が必要です。ただし、子どもが一人で通える場合は、一人で通所することもできます。センターによっては、送迎バスを運行しているところもあります。
Q5. 昼食はどうしますか?
お弁当持参が一般的です。一部のセンターでは、みんなで調理実習をして昼食を作ることもあります。
Q6. 高校生も利用できますか?
原則として小学生・中学生(義務教育段階)が対象です。ただし、一部の自治体では高校生向けのプログラムを実施しています。詳しくはお住まいの教育委員会にお問い合わせください。
⚠️ 定員がある場合があります
教育支援センターは、施設の規模やスタッフの人数により、受け入れ人数に上限がある場合があります。利用希望者が多い場合は、待機期間が発生することもあります。早めに教育委員会に相談することをお勧めします。
関連する公的情報リンク
- 🔗 文部科学省「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」令和元年10月25日
- 🔗 文部科学省「不登校への対応について」
- 🔗 文部科学省「教育支援センター(適応指導教室)に関する実態調査」結果(PDF)
- 🔗 文部科学省「令和4年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」(PDF)
- 🔗 文部科学省「教育機会確保法について」
関連記事:不登校と発達障害の支援をさらに深く理解する
教育支援センターでの支援をより効果的に活用するために、関連する支援制度や選択肢についても理解を深めましょう。以下の記事では、お子さんの状況に応じた様々な支援の選択肢を詳しく解説しています。
📚 不登校支援の選択肢
- フリースクールと教育支援センターの違い – 2つの選択肢を徹底比較
- 出席扱い制度7要件 – 自宅学習でも出席扱いになる方法
- オンライン学習完全ガイド – 自宅で学べる環境づくり
- 不登校最新統計2024 – 現状とデータから見る傾向
🏫 進路・進学支援
- 高校進学5つの選択肢 – 不登校・発達障害のある生徒の進学先
- ハローワーク専門支援 – 就労に向けた専門窓口の活用法
🧠 発達障害の理解と支援
- 発達障害の基礎知識 – 特性と支援方法を理解する
- 発達障害者支援センターの使い方 – 専門的な相談・支援を受ける方法
- ペアレント支援プログラム – 保護者向けのトレーニング
📖 総合ガイド
- 発達障害と不登校支援の完全ガイド – すべての支援情報を網羅したピラー記事
これらの記事を組み合わせて読むことで、お子さんの状況に最適な支援の組み合わせを見つけることができます。教育支援センターのスタッフや在籍校の先生に、これらの選択肢について相談することもおすすめです。
まとめ:教育支援センターは「もう一つの学びの場」
この記事では、教育支援センター(適応指導教室)の使い方について解説しました:
- 教育支援センターとは:教育委員会が設置する公的支援機関。全国約1,700箇所、無料で利用可能。
不登校やその傾向にある小学生・中学生が、学習支援、体験活動、相談を受けられます。
- フリースクールとの違い:公的機関(無料)vs 民間(有料)。教育支援センターは原則として出席扱いになる。
費用面で選ぶなら教育支援センター、自由な雰囲気を重視するならフリースクールも検討しましょう。
- 出席扱いの仕組み:文部科学省の通知により、教育支援センターでの指導は「出席扱い」とすることができる。
在籍校の校長判断により、通知表の出席日数にカウントされます。
- 利用の流れ:教育委員会に問い合わせ→在籍校と相談→面談・見学→通所開始→定期的な通所。
週1回から始めて、徐々に通所日数を増やすことができます。
- 活動内容:①学習支援、②体験活動、③相談・カウンセリング。
一人ひとりのペースに合わせた柔軟な支援が特徴です。
教育支援センターは、「学校に戻るため」の場所ではなく、「子どもが安心して学べるもう一つの場所」です。文部科学省も「学校復帰のみを目標としない」と明言しています。大切なのは、子どもが自分らしく成長できる環境を見つけることです。
次のステップとして、お住まいの市区町村の教育委員会に連絡し、教育支援センターの情報を聞いてみましょう。見学だけでもOKです。「ここなら通えるかも」と感じる場所が見つかることを願っています。