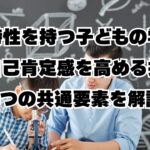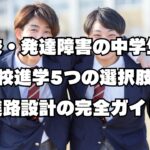発達特性を持つ子どもの学習意欲と自己肯定感を高める指導法|4つの共通要素を解説 「発達特性を持つ子どもが、なかなか学習に意欲を示さない」「自信を持てず、すぐに諦めてしまう」——こうした悩みを抱えている教育関係者や保護者の方は少なくありません。 この記事では、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注…
発達障害者支援センターの使い方:無料相談から就労支援まで【全国90箇所・完全ガイド】
- 公開日:2025/11/7
- 最終更新日:
- 特性別ガイド
- 発達障害者支援センターの使い方:無料相談から就労支援まで【全国90箇所・完全ガイド】 はコメントを受け付けていません
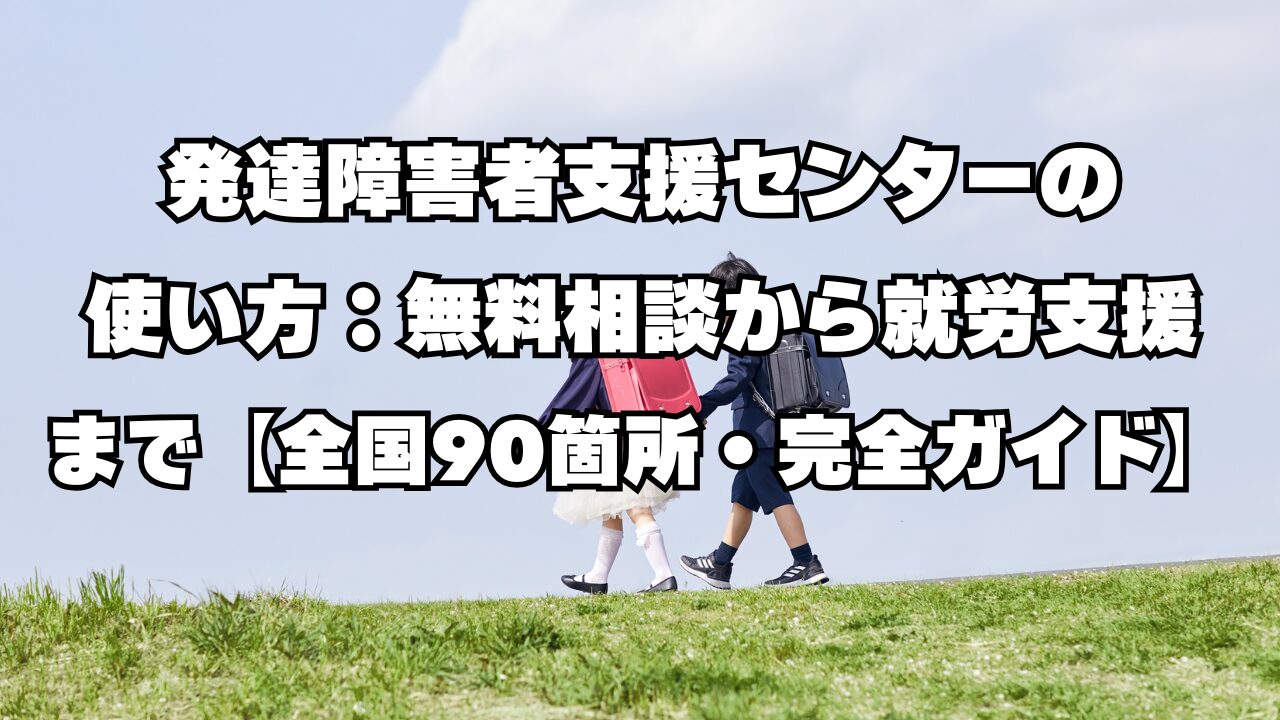
発達障害者支援センターの使い方:無料相談から就労支援まで【全国90箇所・完全ガイド】
「子どもの発達が気になるけど、どこに相談すればいいの?」「発達障害の診断を受けたけど、この先どうすれば…」そんな不安を抱えていませんか?
この記事では、発達障害者支援センターの使い方について、サービス内容、利用方法、実際の相談例を詳しく解説します。
💡 発達障害者支援センターは「総合案内窓口」
発達障害者支援センターは、大きな駅の「総合案内所」のようなものです。どの路線に乗ればいいかわからないとき、案内所で聞けば、目的地までの最適なルートを教えてもらえます。同じように、発達障害に関する悩みをどこに相談すればいいか、どんな支援が使えるか、専門スタッフが一緒に考えて、適切な支援先へつないでくれます。
この記事を読めば、発達障害者支援センターで受けられるサービスと利用の流れがわかります。(予約方法から相談内容まで、初めての方でも安心して利用できます!)
注:発達障害の支援機関は様々です。この記事では都道府県・指定都市が設置する「発達障害者支援センター」に焦点を当てていますが、他にも市区町村の相談窓口、医療機関、民間事業所など多様な選択肢があります。
⚠️ 医療行為は行いません
発達障害者支援センターは相談・支援機関であり、医療機関ではありません。診断や治療が必要な場合は、医療機関(小児科、児童精神科、精神科等)を受診してください。センターでは必要に応じて適切な医療機関を紹介しています。
発達障害者支援センターとは?
発達障害者支援センターは、発達障害者支援法(平成16年法律第167号)に基づき、都道府県・指定都市が設置する公的な支援機関です。全国に約90箇所設置されており、発達障害のある方やそのご家族が、地域で安心して生活できるよう、様々な支援を無料で提供しています。
出典:国立障害者リハビリテーションセンター 発達障害情報・支援センター
設置主体
都道府県・指定都市
発達障害者支援法に基づく公的機関
箇所数
全国約90箇所
各都道府県・指定都市に最低1箇所
(令和5年度時点)
費用
無料
相談・支援サービスはすべて無料で利用可能
対象となる方
以下の方が利用できます:
- 発達障害のある方本人(子どもから大人まで、年齢制限なし)
- ご家族(保護者、きょうだい、配偶者等)
- 支援者(教育・保育・福祉・医療関係者等)
診断の有無は問いません。「発達が気になる」「もしかして発達障害かも?」という段階でも相談できます。
💡 診断前の相談は「健康診断」のようなもの
診断を受ける前に支援センターに相談するのは、病院に行く前に健康診断を受けるようなものです。「なんとなく調子が悪い」段階で健康診断を受けることで、必要なら専門医を紹介してもらえます。同じように、「発達が気になる」段階で相談することで、必要なら医療機関や療育機関を紹介してもらえます。早めの相談が、適切な支援への近道です。
お住まいの地域のセンターを探す方法
まずは、お住まいの地域の発達障害者支援センターを探しましょう。以下の方法で簡単に見つかります。
方法1:全国センター一覧から探す(最も確実)
国立障害者リハビリテーションセンターのウェブサイトで、全国のセンター一覧を公開しています:
🔗 全国の発達障害者支援センター一覧(国立障害者リハビリテーションセンター)
このページでは、都道府県別にセンターの名称、所在地、電話番号、ウェブサイトが掲載されています。お住まいの都道府県をクリックすると、詳細情報が表示されます。
方法2:厚生労働省のポータルサイトから探す
厚生労働省も発達障害に関する情報ポータルを提供しています:
方法3:市区町村の窓口に問い合わせる
お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口(福祉課、障害福祉課等)に電話で問い合わせても、最寄りのセンターを教えてもらえます。
窓口への問い合わせ例
- 「発達障害者支援センターの連絡先を教えてください」
- 「子どもの発達について相談できる公的機関はありますか?」
- 「発達障害の相談窓口を探しています」
3つの主要サービス
発達障害者支援センターでは、主に3つのサービスを提供しています。
①相談支援
発達障害に関するあらゆる相談に対応します。心理士、社会福祉士、保健師等の専門スタッフが、面談(予約制)、電話、メール等で相談を受け付けます。
相談できる内容(具体例)
- 乳幼児期:言葉の遅れ、視線が合わない、こだわりが強い
- 保育園・幼稚園:集団行動が苦手、指示が通りにくい、友達とトラブルが多い
- 小中学校:授業についていけない、不登校、いじめられる
- 高校・大学:進路選択、学習方法、人間関係
- 就職活動:自分に合った仕事がわからない、面接が苦手
- 職場:仕事のミスが多い、上司や同僚とうまくいかない
- 家族:子どもとの接し方、家族の理解が得られない
- 制度利用:療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害年金
実際の相談例
【例1:5歳児の保護者】
「幼稚園の先生から『落ち着きがない』『指示が通りにくい』と言われました。家でもこだわりが強くて、予定が変わるとパニックになります。発達障害でしょうか?」
→センターの対応:まず詳しくお話を伺い、必要に応じて医療機関(小児科・児童精神科)や児童発達支援事業所を紹介。並行してセンターでも定期的な相談を継続。
【例2:中学2年生の保護者】
「ADHDの診断を受けていますが、中学に入ってから不登校になりました。高校進学が心配です。」
→センターの対応:教育支援センター(適応指導教室)や通信制高校の情報提供。必要に応じて学校との連携調整。進路相談も継続的に実施。
【例3:25歳の成人本人】
「就職しましたが、仕事のミスが多く、上司から怒られてばかりです。もしかして発達障害でしょうか?」
→センターの対応:医療機関での診断を勧めつつ、ハローワークの専門支援窓口や地域障害者職業センターを紹介。職場での合理的配慮について助言。
💡 相談支援は「道案内」
センターの相談支援は、初めての街での「道案内」に例えられます。目的地(解決したい悩み)はわかっているけど、どの道を通ればいいかわからないとき、地元の人に聞けば最短ルートを教えてもらえます。センターの相談も同じで、「診断を受けたい」「療育を受けたい」という目的地に向かって、どの機関をどの順番で訪れればいいか、専門スタッフが道案内してくれます。
②発達支援
本人や家族が、発達障害の特性を理解し、適切な対応方法を学ぶための支援を行います。
- 本人向けプログラム:ソーシャルスキルトレーニング(SST)、学習支援、就労準備プログラム等
- 家族向けプログラム:ペアレントトレーニング、家族教室、保護者交流会等
- 支援者向け研修:教員、保育士、福祉職員等への研修・コンサルテーション
💡 発達支援は「取扱説明書の読み方講座」
発達支援は、複雑な機械の「取扱説明書の読み方講座」に例えられます。新しい家電を買ったとき、説明書を読んでも難しくてわからないことがあります。そんなとき、メーカーの講習会に参加すると、「この機能はこう使うんですよ」と実演してもらえて、一気に使いこなせるようになります。発達支援も同じで、発達障害の特性という「説明書」の読み方を、専門家と一緒に学ぶことで、子どもとの関わり方が格段にスムーズになります。
③就労支援
発達障害のある方の就職や職場定着を支援します。
- 就労相談:職業適性の相談、就職活動の進め方、履歴書・面接対策等
- 関係機関との連携:ハローワーク(障害者雇用サポーター)、地域障害者職業センター、就労移行支援事業所等との連携
- 職場への助言:雇用企業への支援方法の助言、合理的配慮の提案(本人・家族の同意が必要)
- 職場定着支援:就職後の定期的なフォロー、職場訪問
学生・若年層
対象:中学生〜20代前半
内容:進路選択、職業訓練校の情報提供、就職活動支援
成人
対象:20代後半以降
内容:転職相談、職場適応、キャリア形成、在職者支援
利用方法と流れ(5ステップ)
発達障害者支援センターの利用は、以下の流れで進みます。具体的な手順を見ていきましょう。
ステップ1: お住まいの地域のセンターを探す
前述の「お住まいの地域のセンターを探す方法」を参考に、最寄りのセンターを見つけてください。
ステップ2: 電話またはメールで相談予約
センターに連絡し、相談の予約を取ります。多くのセンターでは電話予約が一般的ですが、メールやウェブフォームでの予約を受け付けているところもあります。
予約時に伝える内容
- 相談者の名前(本人または保護者)
- 本人の年齢・性別
- 相談したい内容(簡単に)例:「子どもの発達について」「就職について」
- 診断の有無(ある場合は診断名)
- 希望する日時(平日の日中が多い。複数候補があると予約しやすい)
- 連絡先(電話番号、メールアドレス)
予約の電話例:
「初めて相談したいのですが、予約はできますか?5歳の息子の発達について相談したいです。幼稚園の先生から『落ち着きがない』と言われて心配しています。来週の平日であれば、いつでも大丈夫です。」
初回相談は通常1〜2週間後に設定されることが多いですが、センターの混雑状況により前後します。緊急性が高い場合はその旨を伝えてください。
💡 予約は「病院の初診予約」と同じ
センターの予約は、病院で初めて診察を受けるときの予約と同じです。専門医の初診予約は、検査や診察に十分な時間を確保するため、数週間先になることがあります。支援センターも同じで、初回相談では丁寧にお話を聞くため、1〜2時間程度の時間を確保します。余裕を持って予約することで、じっくり相談できます。
ステップ3: 初回相談(面談)
センターに来所し、専門スタッフ(心理士、社会福祉士、保健師等)と面談します。
初回相談の内容:
- これまでの成育歴や生活状況のヒアリング(生まれてから現在までの発達の様子)
- 現在困っていることの整理(具体的なエピソード)
- 家族構成や生活環境の確認
- これまで受けた支援や相談の履歴
- 必要な支援の検討
- 今後の方針の相談
初回相談に持参すると良いもの
- 母子健康手帳(乳幼児の場合)
- 診断書や医療機関の紹介状(ある場合)
- 療育手帳や精神障害者保健福祉手帳(ある場合)
- 学校の通知表や個別の教育支援計画(学齢期の場合)
- 困っていることをメモしたもの(具体的なエピソード)
- 服薬している場合はお薬手帳
面談時間は通常1〜2時間程度です。リラックスして、気になることを何でも相談してください。「こんなこと聞いていいのかな?」と思うことでも、遠慮なく話してください。
初回相談での質問例:
- 「診断を受けた方がいいでしょうか?どこの病院がいいですか?」
- 「療育手帳は取得した方がいいですか?」
- 「学校にどう説明すればいいですか?」
- 「使える福祉サービスはありますか?」
ステップ4: 支援計画の作成
初回相談の内容をもとに、専門スタッフが支援計画を提案します。
- センターで継続支援を受ける場合:定期的な相談(月1回程度)、プログラムへの参加等
- 他機関を紹介する場合:医療機関、療育機関、福祉サービス事業所、教育支援センター等
- 複数機関と連携する場合:センター、医療、福祉、教育が連携して支援
💡 支援計画は「旅行プランの作成」
支援計画を立てるのは、旅行代理店でプランを相談するようなものです。「温泉でゆっくりしたい」「観光地を回りたい」という希望を伝えると、旅行のプロが最適なルートや宿を提案してくれます。支援計画も同じで、「学校に行けるようになりたい」「仕事を見つけたい」という希望を伝えると、支援のプロが、どこでどんな支援を受ければ目標に近づけるか、一緒に考えてくれます。
ステップ5: 継続支援または他機関への紹介
支援計画に基づき、以下のいずれかの形で支援が進みます。
パターンA: センターで継続支援
- 定期的な面談(月1回程度、必要に応じて頻度調整)
- プログラムへの参加(SST、ペアレントトレーニング等)
- 必要に応じて他機関との連絡調整
- 年1回程度の支援計画見直し
パターンB: 他機関への紹介
- 医療機関:診断・治療が必要な場合(児童精神科、精神科等)
- 児童発達支援・放課後等デイサービス:療育が必要な場合
- 教育支援センター:不登校支援が必要な場合
- 就労支援機関:就労支援が必要な場合(ハローワーク、地域障害者職業センター、就労移行支援事業所等)
紹介先への連絡や引継ぎは、本人・家族の同意を得た上で、センターが行います。紹介状や情報提供書を作成してくれることもあります。
他の支援機関との連携
発達障害者支援センターは、単独で支援を完結するのではなく、地域の様々な機関と連携しながら支援を行います。
医療機関
連携内容:診断、治療、投薬、医学的見地からの助言
対象:診断が必要な方、医療的ケアが必要な方
教育機関
連携内容:学校での支援体制づくり、個別の教育支援計画、合理的配慮
対象:在学中の児童生徒
福祉サービス
連携内容:児童発達支援、放課後等デイサービス、就労移行支援
対象:療育や就労支援が必要な方
就労支援機関
連携内容:ハローワーク、地域障害者職業センター
対象:就職を目指す方、在職中の方
このように、発達障害者支援センターは「ハブ(中心)」となり、必要な支援機関を結びつける役割を果たします。
💡 センターの連携は「コンシェルジュサービス」
支援センターの連携機能は、ホテルのコンシェルジュに例えられます。宿泊客が「美味しいレストランを知りたい」「観光ツアーを予約したい」と相談すると、コンシェルジュが最適な店やツアーを紹介し、予約まで手配してくれます。支援センターも同じで、「診断を受けたい」「療育を受けたい」という相談に対して、適切な機関を紹介し、必要なら連絡調整まで行ってくれます。一箇所に相談するだけで、必要な支援先が見つかる便利なサービスです。
よくある質問
Q1. 利用に診断書は必要ですか?
診断書は必須ではありません。「発達が気になる」「もしかして発達障害かも?」という段階でも相談できます。診断が必要かどうかも含めて相談できます。ただし、福祉サービス(児童発達支援、放課後等デイサービス等)を利用する場合は、後日診断書や意見書が必要になることがあります。
Q2. 何回でも相談できますか?
継続的に相談できます。ただし、センターの混雑状況により、相談頻度や期間が調整されることがあります。長期的な支援が必要な場合は、他の支援機関(医療機関、福祉サービス事業所等)と併用することもあります。
Q3. 家族以外の支援者(教員等)も相談できますか?
できます。教員、保育士、福祉職員等の支援者からの相談も受け付けています。ただし、本人や家族に関する個別具体的な相談の場合は、本人・家族の同意が必要です。一般的な支援方法についての相談であれば、同意なしでも可能です。
Q4. 他県に住んでいても利用できますか?
原則として、センターが設置されている都道府県・指定都市に在住・在勤・在学している方が対象です。他県の方は、お住まいの地域のセンターをご利用ください。ただし、引越し前後の移行期間など、特別な事情がある場合は相談可能なこともあります。
Q5. センターと医療機関の違いは?
センターは相談・支援機関であり、診断や治療は行いません。診断が必要な場合は、医療機関(小児科、児童精神科、精神科等)を受診してください。センターでは、地域の医療機関の情報提供や紹介も行っています。診断後の生活支援や福祉サービスの利用については、センターが強力にサポートします。
Q6. 相談内容は秘密にしてもらえますか?
はい。センターのスタッフには守秘義務があります。相談内容が本人・家族の同意なく外部に漏れることはありません。ただし、他機関との連携が必要な場合は、事前に同意を得た上で、必要最小限の情報を共有します。
⚠️ 緊急時の対応
発達障害者支援センターは、緊急の危機対応を行う機関ではありません。自傷他害の恐れがある、虐待が疑われる等の緊急事態の場合は、以下の緊急対応機関にご連絡ください:
・警察(110番)
・児童相談所虐待対応ダイヤル(189)
・精神科救急医療情報センター(都道府県により名称・連絡先が異なります)
関連する公的情報リンク
- 🔗 国立障害者リハビリテーションセンター 発達障害情報・支援センター
- 🔗 全国の発達障害者支援センター一覧
- 🔗 厚生労働省 発達障害施策
- 🔗 厚生労働省 発達障害者支援
- 🔗 発達障害者支援法(e-Gov法令検索)
関連記事:発達障害と不登校の支援をさらに深く理解する
発達障害者支援センターでの支援をより効果的に活用するために、関連する支援制度や選択肢についても理解を深めましょう。以下の記事では、お子さんの状況に応じた様々な支援の選択肢を詳しく解説しています。
📚 教育支援の選択肢
- 教育支援センターの使い方 – 不登校の子どもへの公的支援
- フリースクールと教育支援センターの違い – 2つの選択肢を徹底比較
- オンライン学習完全ガイド – 自宅で学べる環境づくり
- 出席扱い制度7要件 – 自宅学習でも出席扱いになる方法
💼 進路・就労支援
- 高校進学5つの選択肢 – 発達障害のある生徒の進学先
- ハローワーク専門支援 – 就労に向けた専門窓口の活用法
👨👩👧 家族支援・基礎知識
- ペアレント支援プログラム – 保護者向けのトレーニング
- 発達障害の基礎知識 – 特性と支援方法を理解する
- 不登校最新統計2024 – 現状とデータから見る傾向
📖 総合ガイド
- 発達障害と不登校支援の完全ガイド – すべての支援情報を網羅したピラー記事
これらの記事を組み合わせて読むことで、お子さんの状況に最適な支援の組み合わせを見つけることができます。発達障害者支援センターの相談員に、これらの選択肢について質問することもおすすめです。
まとめ:発達障害者支援センターは「困ったときの総合窓口」
この記事では、発達障害者支援センターの使い方について解説しました:
- 発達障害者支援センターとは:都道府県・指定都市が設置する公的支援機関。全国約90箇所、無料で利用可能。
診断の有無に関わらず、発達障害に関するあらゆる相談ができます。
- センターの探し方:国立障害者リハビリテーションセンターのウェブサイトで全国一覧を検索。
お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口に問い合わせても教えてもらえます。
- 3つの主要サービス:①相談支援(発達・生活・就労等)、②発達支援(本人・家族・支援者向けプログラム)、③就労支援(就職活動・職場定着)。
年齢や状況に応じた多様な支援を提供しています。
- 利用の流れ:センターを探す→電話予約→初回相談(1〜2時間)→支援計画作成→継続支援または他機関紹介。
初回相談では、困っていることを何でも話せます。リラックスして相談してください。
- 他機関との連携:医療、教育、福祉、就労支援機関と連携し、包括的な支援を提供。
センターが「ハブ」となり、必要な支援先を紹介・調整してくれます。
発達障害者支援センターは、発達障害に関する「困ったときの総合窓口」です。「こんなこと相談していいのかな?」と迷ったら、まずは気軽に電話してみてください。専門スタッフが丁寧にお話を聞き、一緒に解決策を考えてくれます。
次のステップとして、全国の発達障害者支援センター一覧からお住まいの地域のセンターを検索し、気になることがあれば予約を取ってみましょう。早めの相談が、お子さんやご家族の安心した生活につながります。