学年別・教科別 問題生成ツール一覧 お子様の学年と教科を選んで、文部科学省の学習指導要領に準拠した学習プリントを無料で作成できます。 📚 小学1年生 国語 - ひらがな・カタカナ・漢字練習 算数 - 数の数え方・たし算・ひき算 生活 - 季節・身の回りの観察 📚 小学…
発達遅延と発達障害の違いとは?時間をかければ追いつける可能性と保護者ができること
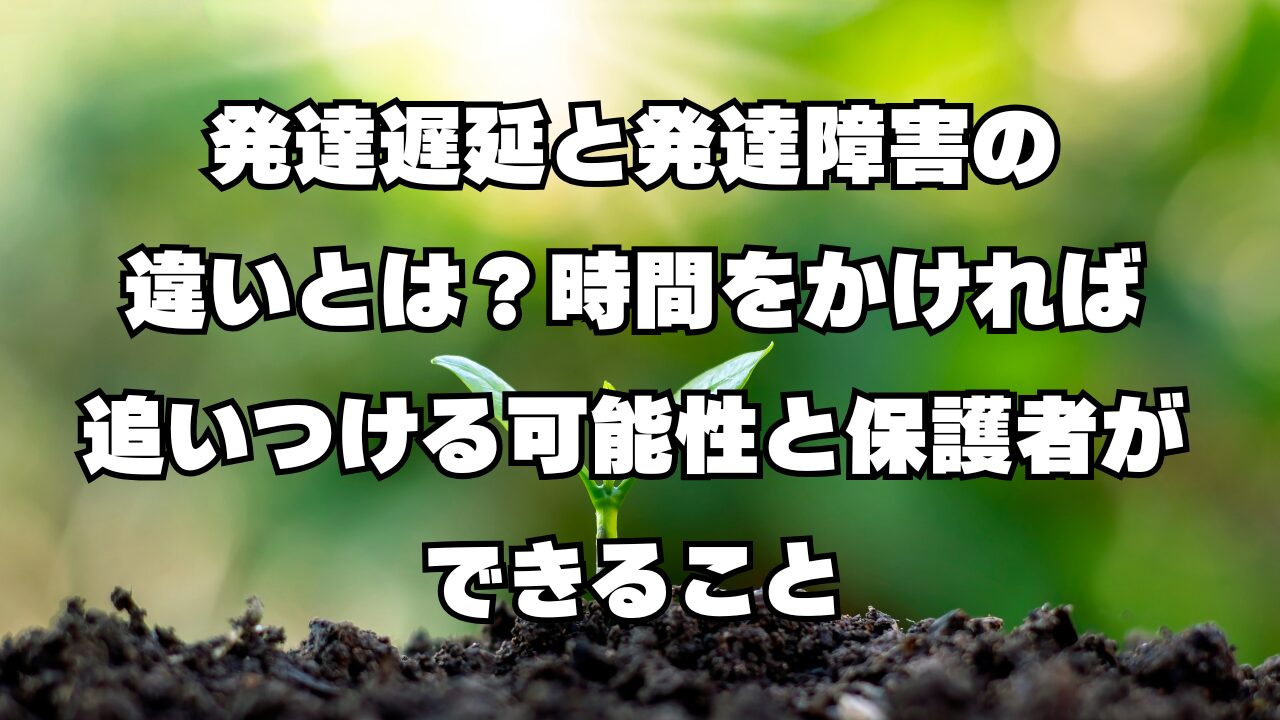
「うちの子、周りより発達が遅い気がする…」
「これって発達障害なのかな?」
そんな不安を抱えている保護者の方へ。最近、精神科医の樺沢紫苑先生の動画で語られた「発達障害ではなく、発達遅延です」という言葉が、多くの保護者の心に希望の光を灯しています。
この記事では、発達遅延と発達障害の違い、そして時間をかければ追いつける可能性について、専門的な知見と保護者の実体験を交えながら、わかりやすく解説します。
💡 発達遅延は「マラソンのスタート位置の違い」
発達遅延は、マラソンのスタート位置が少し後ろにあるようなものです。スタートが遅れているだけで、走る能力がないわけではありません。周りの子が先に走り出しても、自分のペースで走り続ければ、ゴール(年齢相応の発達)に追いつける可能性があるのです。
お子さまの成長を信じて、一緒に希望を持って向き合っていきましょう。
⚠️ この記事を読む前に知っておいていただきたいこと
この記事は、保護者の方に希望を持っていただくための情報提供を目的としています。ただし、お子さまの発達の状態は個別に大きく異なります。必ず専門医(小児発達外来・児童精神科など)による個別評価を受けてください。この記事の内容は、専門的な診断や治療の代わりになるものではありません。
「発達障害」と「発達遅延」は違う?精神科医が語る新しい視点
精神科医の樺沢紫苑先生がYouTube動画で語った内容が、多くの保護者の心を動かしています。
先生はこう言いました。「発達障害ではなく、発達遅延です」
「障害」ではなく「遅延」という言葉の違い
「障害」という言葉には、どこか固定的で、変わらないという響きがあります。一方、「遅延」という言葉には、「遅れているだけ」「時間をかければ追いつける」という希望が含まれています。
「発達障害」という言葉のイメージ
印象:固定的、変わらない、生涯続く
保護者の気持ち:「この子はずっとこのままなのか…」という絶望感を抱きやすい
「発達遅延」という言葉のイメージ
印象:一時的、時間をかければ追いつける、成長の可能性がある
保護者の気持ち:「時間をかければ大丈夫かもしれない」という希望を持てる
樺沢先生が伝えたかったこと
樺沢先生の動画では、以下のようなポイントが語られています:
- 発達障害の子どもは、正常な子どもより1〜2周遅れで走り続けているだけ
- 適切なサポートがあれば、20歳頃までに追いつける可能性がある
- アメリカの研究では、10代で発達障害と診断された子どもの半分以上が、20歳を過ぎた時点で普通に働いて生活していた
この視点は、多くの保護者に「諦めなくていいんだ」という希望を与えました。
医学的には「発達遅延」とは何か?正確な定義を知る
希望的な視点は大切ですが、正確な情報を知ることも同じくらい重要です。医学的に「発達遅延」とはどのように定義されているのでしょうか。
発達遅延の医学的定義
発達遅延(Developmental Delay)とは、子どもの発達期間中に、身体、学習、言語、または行動の領域において機能の障害や遅れが見られる状態を指します。
具体的には、以下の領域における遅れとして定義されます:
発達遅延が見られる主な領域
- 言語発達および発話:言葉が遅い、会話が苦手など
- 運動発達:歩く・走るなどの粗大運動、手先の細かい動作など
- 認知的発達:理解力、記憶力、問題解決能力など
- 社会性-情緒的発達:対人関係、感情のコントロールなど
この定義の背景要因や看護的なアセスメント方法を詳しく知りたい保護者の方は、専門用語集で確認することで、日常の観察ポイントが明確になります。詳細はナース専科の小児発達遅延用語集で確認できます。
発達遅延と発達障害の関係
ここで重要なのは、発達遅延は「広範な発達障害児の総称」として使われることもあるという点です。つまり、医学的には「発達遅延」と「発達障害」を明確に区別しているわけではありません。
💡 発達遅延と発達障害の関係は「風邪と肺炎」の関係に似ている
風邪の症状(咳、熱)は、数日で治ることもあれば、肺炎に進行することもあります。同様に、発達の遅れ(発達遅延)は、時間とともに追いつくこともあれば、より持続的な特性(発達障害)として残ることもあります。初期段階では区別が難しく、経過観察と適切な対応が重要です。
専門家の間では、以下のような理解が一般的です:
- 一過性の遅れ(環境要因や一時的な未熟性)は、適切な支援で追いつく可能性が高い
- 持続的な遅れ(自閉スペクトラム症、注意欠如・多動症、学習障害など)は、生涯にわたって特性として続くことが多い
発達遅延が一時的なものか持続的な特性かを判断するための違いを、具体的な発達特性の例とともに知りたい方は、療育専門サイトの解説が役立ちます。詳細はONEPLAY.GIFTEDの発達の遅れと発達障害の違い解説記事で確認できます。
「20歳までに50%が追いつく」は本当?数字の正確性を検証
樺沢先生の動画では「20歳頃までに追いつける可能性がある」「半分以上が普通に働いて生活していた」という話がありました。この数字は本当なのでしょうか?
一次ソースは見つかっていない
結論から言うと、「発達遅延が20歳頃までに約50%の確率で追いつく」という特定の数値を示す医学論文や公的データは、現時点では確認されていません。
ただし、これは「その話が完全に間違っている」という意味ではありません。
類似した研究データは存在する
特定の領域、特に言語発達の遅れについては、追いつく可能性を示す研究があります:
言語発達遅延に関する研究結果
- 幼児期に言葉が遅い子どもの約50%〜70%が、就学前までに同年代と同じレベルまで追いつくという報告があります
- ただし、7歳時点で約20%が言語障害を残す可能性もあります
- 受容性言語(理解力)の遅れがある場合は、リスクが高くなります
また、全体的な発達遅延(Global Developmental Delay)については:
- 2歳時点で発達遅延を示す子どもの約半数が3歳までに回復するという報告もあります
- ただし、これは主に軽度の一過性遅延(環境要因や一時的な未熟性)の場合です
1歳半頃の発達遅れが指摘された場合の自然回復の可能性や家庭でのサポート方法を具体的に知りたい保護者の方は、専門スクールのガイドが参考になります。詳細はコペルプラスの1歳半健診と発達遅れの家庭支援記事で確認できます。
なぜ「50%」という数字が一人歩きするのか
おそらく、樺沢先生は以下の要素を総合して「約半分くらいは追いつく可能性がある」と伝えたかったのだと考えられます:
- 臨床経験からの感覚
- 言語発達遅延などの研究データ
- 教育現場での実感(「大人になる頃には目立たなくなる子も多い」)
⚠️ 数字の扱いに注意
「発達遅延全体について、20歳までに50%が追いつく」という形で一般化するのは正確ではありません。追いつく可能性は、遅延のタイプ(言語・運動・認知)、重症度、支援の有無によって大きく異なります。お子さまの状態については、必ず専門医による個別評価を受けてください。
それでも希望を持っていい理由|成長と支援の可能性
数字の正確性については注意が必要ですが、それでも保護者の方々が希望を持っていい理由はたくさんあります。
子どもの脳は成長し続ける
子どもの脳は、大人が思っている以上に柔軟で、成長の可能性を秘めています。特に幼児期から学童期にかけては、適切な支援と環境によって大きく発達を促すことができる「黄金期」とされています。
早期介入の効果は実証されている
医学的な研究でも、早期発見と早期介入が、子どもの生活の質(QOL)の向上に大きく寄与することが示されています。
早期介入の重要性を脳の可塑性という観点から理解したい方は、子どもの頃の習慣形成が長期的に影響する理由が詳しくわかります。詳細は発達アピラの早期発見・早期介入と脳の可塑性ページで確認できます。
「追いつく」の意味を正しく理解する
ここで重要なのは、「追いつく」という言葉の意味です。
「追いつく」とは、必ずしも「定型発達の子とまったく同じになる」という意味ではありません。多くの場合、以下のような意味で使われます:
- 日常生活に大きな支障がないレベルまで成長する
- 自分の得意なことを活かして、社会で役割を果たせるようになる
- 困りごとを自分で工夫したり、周囲に助けを求めたりできるようになる
完璧を目指すのではなく、お子さまなりの成長と幸せを見守るという視点が大切です。
保護者ができる具体的な改善方法|生活習慣とサポート
樺沢先生の動画では、発達遅延の改善に役立つ具体的な方法も紹介されています。これらは医学的にも支持されている内容です。
1. 運動習慣を取り入れる
運動は、脳の発達に非常に重要な役割を果たします。特に、以下のような運動がおすすめです:
おすすめの運動
- 外遊び:公園で走る、ボール遊びなど
- リズム運動:ダンス、縄跳びなど
- バランス運動:平均台、片足立ちなど
- 協調運動:キャッチボール、ドリブルなど
2. 栄養バランスの良い食事
脳の発達には、適切な栄養が不可欠です。特に以下の栄養素を意識してください:
- タンパク質:肉、魚、卵、大豆製品
- DHA・EPA:青魚(サバ、イワシ、サンマ)
- 鉄分:レバー、ほうれん草、ひじき
- ビタミンB群:全粒穀物、緑黄色野菜
3. 規則正しい生活リズム
睡眠と生活リズムは、子どもの発達に大きく影響します。
生活リズムのポイント
- 毎日同じ時間に起きる・寝る
- 十分な睡眠時間を確保する(幼児:10-12時間、学童:9-11時間)
- 朝日を浴びる(体内時計のリセット)
- 食事の時間を一定にする
4. スマホ・タブレットの使用時間を制限する
これは特に重要なポイントです。樺沢先生の動画でも強調されていますが、スマホは1日2時間以上使うとADHD症状のリスクが高まるという研究があります。
⚠️ スマホ・タブレット使用の注意点
1歳児のスクリーンタイムが長いほど、2歳および4歳時のコミュニケーションおよび問題解決の領域における発達遅延のリスクが高いという研究結果があります。できるだけ使用時間を制限し、親子での会話や外遊びの時間を増やしましょう。
5. お子さまのペースを尊重する
最も重要なのは、お子さまのペースを尊重することです。
💡 子どもの成長は「花の開花」に似ている
花にはそれぞれ開花の時期があります。桜は春に咲き、ひまわりは夏に咲きます。無理やり早く咲かせようとしても、花は美しく咲きません。子どもの発達も同じです。その子なりの時期とペースがあり、焦らず見守ることで、美しく花開く可能性があるのです。
個人差を理解する|身長の伸びと発達の関係
発達の個人差を理解するために、身長の伸びとの比較が分かりやすいでしょう。
身長が伸びる時期は人それぞれ
小学生の頃、背の順に並んだ経験はありませんか?前の方にいた子が、中学生になると後ろの方に移動していたり、その逆もあったりします。
身長が伸びる時期は、人によって違います。早く伸びる子もいれば、遅く伸びる子もいます。でも、誰も「なんでお前は背が低いんだ」「努力が足りない」とは言いません。
発達も同じように個人差がある
脳の発達も、身長と同じように個人差があるはずです。早く理解できる子もいれば、時間がかかる子もいます。
それなのに、学校の授業は全員が同じペースで進むことを前提にしています。これは、身長で例えるなら「小学5年生で160cmに到達すること」を前提に授業を進めるようなものです。
身長の場合
個人差の認識:伸びる時期が人それぞれであることは誰もが理解している
周囲の対応:「背が低い」ことを責めたり、「努力が足りない」とは言わない
発達・学習の場合
個人差の認識:個人差があることが十分に理解されていないことが多い
周囲の対応:「なんで分からないの?」「努力が足りない」と言われることがある
個別のペースで学べる環境が必要
身長が伸びる時期が違うように、勉強を理解する時期も違います。それなのに、全員が同じペースで学ぶのは無理があります。
だから、個別のペースで学べる環境が必要なんです。家庭教師や個別指導塾が存在するのは、そのためです。
専門医による評価の重要性|「様子を見る」だけではダメ
ここまで希望的な内容をお伝えしてきましたが、最も重要なのは専門医による適切な評価です。
「様子を見ましょう」は危険な場合もある
よく、保育園や学校で「もう少し様子を見ましょう」と言われることがありますが、これは必ずしも適切なアドバイスとは限りません。
⚠️ 早期発見・早期介入が重要
発達の問題は、早期に発見し、早期に適切な支援を始めることが、将来の生活の質を大きく左右します。「様子を見る」だけで時間を無駄にせず、気になることがあれば専門医に相談してください。
どこに相談すればいい?
発達の心配がある場合、以下の機関に相談できます:
相談できる機関
- 小児発達外来:小児科の中で発達を専門に診る外来
- 児童精神科:子どもの心の問題を専門に診る精神科
- 発達障害者支援センター:全国に約90箇所、無料で相談可能
- 教育支援センター:全国に約1,700箇所、無料で相談可能
- 保健センター:各自治体にあり、発達相談を受け付けています
評価を受けるメリット
専門医による評価を受けることで、以下のようなメリットがあります:
- お子さまの強みと弱みが客観的に分かる
- 具体的な支援方法が明確になる
- 学校や保育園と連携しやすくなる
- 利用できる支援制度(療育、教育支援など)が分かる
- 保護者の不安が軽減される
樺沢紫苑先生の解説動画
この記事で紹介した樺沢紫苑先生の動画はこちらです。発達遅延について、先生ご自身の言葉で詳しく解説されていますので、ぜひご覧ください。
※この動画の内容について、記事内では専門的な資料も交えながら解説しています。
まとめ:発達遅延と発達障害の違い、そして希望を持って向き合うために
この記事では、発達遅延と発達障害の違い、そして時間をかければ追いつける可能性について解説しました。
- 「発達障害」と「発達遅延」の違い:医学的には明確に区別されていませんが、「遅延」という言葉には「時間をかければ追いつける」という希望が含まれています。
ただし、一過性の遅れか持続的な特性かは、個別の評価が必要です。
- 「20歳までに50%が追いつく」という数字:一次ソースは確認されていませんが、言語発達遅延などでは類似したデータがあります。
ただし、追いつく可能性は、遅延のタイプ、重症度、支援の有無によって大きく異なります。
- 希望を持っていい理由:子どもの脳は柔軟で、早期介入によって発達を促すことができます。
「追いつく」とは、定型発達と同じになることではなく、その子なりの成長と幸せを見守ることです。
- 保護者ができること:運動、栄養、規則正しい生活、スマホ制限など、生活習慣の改善が発達を促します。
最も重要なのは、お子さまのペースを尊重することです。
- 専門医による評価の重要性:「様子を見る」だけではなく、早期発見・早期介入が将来の生活の質を左右します。
気になることがあれば、専門医に相談してください。
お子さまの発達が気になる保護者の方へ。
「遅れている」は「ダメ」ではありません。時間をかければ、お子さまなりの成長を遂げる可能性があります。
諦めずに、希望を持って、お子さまのペースを尊重しながら、一緒に歩んでいきましょう。そして、専門家の力も借りながら、お子さまに最適な環境を整えてあげてください。
あなたとお子さまの未来に、たくさんの可能性が開かれることを願っています。




