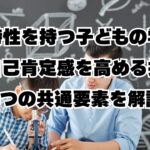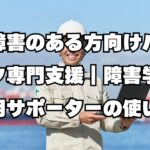発達特性を持つ子どもの学習意欲と自己肯定感を高める指導法|4つの共通要素を解説 「発達特性を持つ子どもが、なかなか学習に意欲を示さない」「自信を持てず、すぐに諦めてしまう」——こうした悩みを抱えている教育関係者や保護者の方は少なくありません。 この記事では、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注…
不登校・発達障害向けオンライン学習完全ガイド|出席扱い制度と教材の選び方
- 公開日:2025/11/7
- 最終更新日:
- 特性別ガイド
- 不登校・発達障害向けオンライン学習完全ガイド|出席扱い制度と教材の選び方 はコメントを受け付けていません
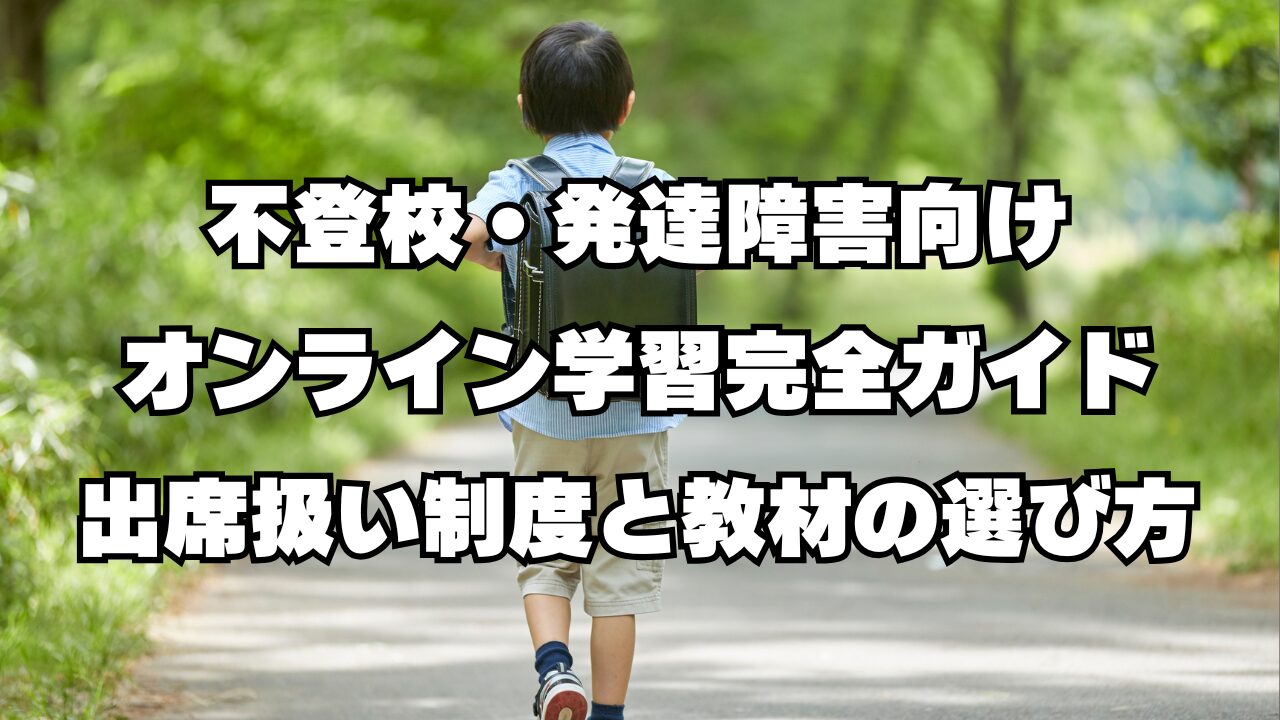
「学校に行けないけど、勉強は遅れてほしくない」「オンライン学習で出席扱いになるって本当?」「うちの子に合うオンライン教材はどれ?」
こうした疑問を持つ保護者の方は少なくありません。実は、文部科学省は令和元年10月の通知で、一定の要件を満たせば自宅でのオンライン学習を「出席扱い」にできると明記しています。
この記事では、不登校・発達障害のある児童生徒向けのオンライン学習活用法について、出席扱い制度の7要件、代表的な教材、選び方のポイントを詳しく解説します。
💡 オンライン学習は「オーダーメイドの洋服」
学校の授業は、「既製品の洋服」のようなものです。多くの人に合うように作られていますが、体型が特殊だと合わないことがあります。オンライン学習は、「オーダーメイドの洋服」です。一人ひとりの体型(学習スタイル、理解度、特性)に合わせて調整できます。自分のペースで、自分に合った方法で学べるのが最大の強みです。
この記事を読めば、あなたのお子さんに合ったオンライン学習の選び方、出席扱いを受けるための手続きがわかります。専門知識は不要です!
注:オンライン学習の方法や教材は多様です。この記事では主要な選択肢を紹介していますが、お子さんの状況により他の選択肢もあります。
⚠️ 出席扱い制度について
文部科学省の通知(令和元年10月25日)に基づく出席扱い制度は、「学校外の公的機関や民間施設等で相談・指導を受けられない場合」に適用されます。教育支援センター(適応指導教室)などの公的支援が優先されます。詳しくは学校または教育委員会に確認してください。
オンライン学習とは:3つのタイプ
オンライン学習の基本
オンライン学習とは、インターネットを活用して自宅で学習する方法です。不登校や発達障害のある児童生徒にとって、以下のようなメリットがあります。
- 自分のペースで学べる:理解できるまで繰り返し学習できる
- 通学の負担がない:体調や精神的な状態に合わせて学習できる
- 個別に最適化:一人ひとりの理解度に合わせた内容
- 視覚的・聴覚的サポート:動画、音声、アニメーションなど多様な表現
3つのタイプ
1. 教材型(オンデマンド)
特徴:録画された動画や教材を自分のペースで学習
代表例:すらら、スタディサプリ、天神
向いている子:自分のペースでじっくり学びたい、繰り返し学習したい
2. ライブ授業型
特徴:リアルタイムで先生の授業を受ける(双方向)
代表例:通信制高校のオンライン授業、一部の学習塾
向いている子:先生とのやり取りがほしい、決まった時間に学習したい
3. 個別指導型
特徴:オンラインで1対1または少人数の個別指導
代表例:家庭教師のオンライン版、個別指導塾のオンラインコース
向いている子:個別に質問したい、手厚いサポートがほしい
💡 3つのタイプは「食事の形態」
オンライン学習の3つのタイプは、「食事の形態」に例えられます。教材型は「冷凍食品」、好きな時に温めて食べられます。ライブ授業型は「レストラン」、決まった時間にシェフ(先生)が作った料理を食べます。個別指導型は「出張シェフ」、あなたの好みに合わせて目の前で調理してくれます。どれが良いかは、生活スタイルと好みによります。
出席扱い制度:7つの要件
出席扱いとは
文部科学省は令和元年10月25日の通知で、一定の要件を満たせば、自宅でのICT等を活用した学習活動を学校の「出席扱い」にできると明記しました。
出席扱いになると、内申書(調査書)の欠席日数が減り、高校進学に有利になる可能性があります。
7つの要件(文部科学省通知)
要件の詳細説明
【要件1】保護者と学校の連携
保護者が学校と定期的に連絡を取り、子どもの学習状況を共有することが必要です。学校側も協力的である必要があります。ペアレント支援プログラムでは、学校との効果的なコミュニケーション方法も学べます。
【要件2】ICT等を活用
パソコン、タブレット、スマートフォンなどを使ったオンライン学習であることが必要です。紙の教材だけでは該当しません。
【要件3】対面指導
完全にオンラインだけではなく、定期的に担任や支援員が家庭訪問等で対面指導を行うことが求められます。
【要件4】計画的な学習プログラム
学習内容が学校の教育課程に沿っており、子どもの理解度に合わせた計画的なプログラムである必要があります。
【要件5】校長の把握
校長が学習状況を把握し、出席扱いの判断を行います。学校によって判断が異なる場合があります。
【要件6】公的支援が受けられない場合
重要:教育支援センター(適応指導教室)など、公的な支援機関で相談・指導を受けられる場合は、そちらが優先されます。オンライン学習による出席扱いは、公的支援が受けられない場合の代替手段です。フリースクールと教育支援センターの違いを理解した上で選択してください。
【要件7】学習活動の評価
学習内容が学校の教育課程に照らして適切かどうか、学校が評価します。
⚠️ 出席扱いは「保証」ではない
7つの要件を満たしても、出席扱いになるかどうかは校長の判断です。学校によって対応が異なる場合があります。必ず事前に学校(担任または教頭)に相談し、出席扱いの可能性を確認してください。詳しくは出席扱い制度の7要件の記事もご覧ください。
代表的なオンライン学習教材
すらら(教材型)
すららは、無学年式のオンライン学習教材で、不登校・発達障害のある児童生徒向けの機能が充実しています。
- 無学年式:学年に関係なく、自分の理解度に合わせて学習できる
- アニメーション解説:視覚的に分かりやすい
- 音声読み上げ:読み書きが苦手な子にも対応
- すららコーチ:学習計画のサポート
- 出席扱い実績:多くの学校で出席扱いの実績あり
費用:月額8,228円~(3教科コース、事業者公表値)
※民間サービス(有料)
スタディサプリ(教材型)
スタディサプリは、プロ講師による動画授業と問題演習が特徴です。
- 動画授業:1回約15分のプロ講師による授業
- 小学4年生~高校3年生対応:幅広い学年に対応
- 学び直し:前の学年の内容も学習可能
- 低価格:比較的安価で始められる
費用:月額2,178円(ベーシックコース、事業者公表値)
※民間サービス(有料)
天神(教材型)
天神は、買い切り型のデジタル教材で、インターネット接続不要で学習できます。
- 買い切り型:月額料金ではなく、学年・教科ごとの買い切り
- オフライン学習:ネット環境がなくても使える
- プリント印刷:紙での学習も可能
- 発達障害対応:特別支援教育版もあり
費用:学年・教科により異なる(買い切り、数万円~、事業者公表値)
※民間サービス(有料)
通信制高校のオンライン授業(ライブ授業型)
一部の通信制高校では、リアルタイムのオンライン授業を提供しています。
- 双方向授業:先生に質問できる
- 高校の単位取得:高校の正式な授業として認められる
- 学校のサポート:担任やカウンセラーのサポートあり
※通信制高校の学費は年間20~100万円程度(学校により大きく異なる、事業者公表値)。詳しくは高校進学の5つの選択肢をご覧ください。
💡 教材選びは「靴選び」
オンライン学習教材を選ぶことは、「靴選び」に似ています。どんなに高級な靴でも、足に合わなければ歩けません。すららは「オーダーメイドのスニーカー」(無学年式で柔軟)、スタディサプリは「軽量ランニングシューズ」(安価で手軽)、天神は「頑丈な登山靴」(ネット不要で安定)。子どもの足(学習スタイル)に合った靴を選びましょう。
発達障害のある子どもに適した機能
発達障害の種類と適した機能
【ASD(自閉スペクトラム症)】
- 視覚的な教材:図、イラスト、アニメーションが豊富
- 構造化された学習:明確な手順、予測可能な流れ
- 静かな環境:自宅で集中して学習できる
- 一定のルーチン:毎日同じ時間に学習する習慣づけ
【ADHD(注意欠如・多動症)】
- 短時間の学習単位:15分程度の短い動画や問題
- ゲーム要素:ポイント、レベルアップなどのモチベーション機能
- 即時フィードバック:問題を解いたらすぐに正誤が分かる
- 動きを取り入れる:タブレットを使った操作、体を動かしながら学習
【LD(学習障害)】
- 読み上げ機能:テキストを音声で読み上げる(読字障害対応)
- 音声入力:キーボードを使わずに答えられる(書字障害対応)
- 拡大・色変更:文字の大きさや背景色を調整できる
- 繰り返し学習:同じ内容を何度でも復習できる
発達障害の特性について詳しくは、発達障害の基礎知識をご覧ください。また、発達障害者支援センターでは、お子様の特性に合った学習方法について専門的なアドバイスを受けられます。
教材選びでチェックすべき機能
- 無学年式(学年に関係なく、理解度に合わせて学習できる)
- 音声読み上げ機能(読むのが苦手な子に対応)
- アニメーションや動画(視覚的に理解しやすい)
- ゲーム要素(モチベーション維持)
- 保護者向け管理画面(学習状況を確認できる)
- 出席扱い実績(実際に出席扱いになった例があるか)
オンライン学習の選び方
選び方の5ステップ
子どものタイプ別おすすめ
自分のペースでじっくり学びたい子
→ 教材型(すらら、スタディサプリ、天神)
先生とやり取りしたい子
→ ライブ授業型、個別指導型
読み書きが苦手な子(LD)
→ 音声読み上げ機能がある教材(すらら、天神の特別支援教育版)
集中が続かない子(ADHD)
→ 短時間の学習単位、ゲーム要素がある教材(すらら、スタディサプリ)
視覚的な情報が得意な子(ASD)
→ アニメーション、図解が豊富な教材(すらら、スタディサプリ)
💡 無料体験は「試着」
オンライン学習の無料体験は、「洋服の試着」です。カタログ(ウェブサイト)でどんなに良さそうに見えても、実際に着て(使って)みないと分かりません。色(デザイン)は良くても、サイズ(機能)が合わないこともあります。多くのサービスが無料体験を提供しているので、必ず子ども自身に使ってもらい、反応を見てから決めましょう。
オンライン学習を成功させるコツ
環境づくり
【学習場所】
- 静かで集中できる場所を確保する
- できれば専用のデスク・椅子を用意する
- テレビやゲーム機など、気が散るものを遠ざける
- 適度な明るさと温度を保つ
【学習時間】
- 毎日決まった時間に学習する習慣をつける
- 最初は短時間(15~30分)から始める
- 子どもの集中力に合わせて休憩を入れる
- 無理に長時間やらせない
保護者のサポート
【見守りと関与のバランス】
- 最初は一緒に操作方法を確認する
- 慣れてきたら、適度な距離で見守る
- 毎日「今日は何を勉強したの?」と声をかける
- できたことを具体的に褒める
ペアレント支援プログラムでは、お子様との効果的な関わり方について学べます。
【学習状況の確認】
- 保護者向け管理画面で進捗を確認する
- 週に1回程度、一緒に振り返りをする
- 学校にも定期的に報告する(出席扱いを目指す場合)
成功のためのチェックポイント
- 子どもが「楽しい」「分かる」と感じているか
- 無理なく続けられる学習時間・量か
- 少しずつでも進んでいる実感があるか
- 保護者が過度に干渉しすぎていないか
- 学校との連携が取れているか(出席扱いを目指す場合)
つまずいたときの対処法
子どもがやる気を失ったら
- 無理に続けさせない(一度休憩する)
- 教材や学習方法を見直す
- 小さな目標を設定し、達成感を味わわせる
- サポート窓口に相談する(多くのサービスにあり)
技術的なトラブル
- インターネット接続を確認する
- デバイスの再起動を試す
- サービスのサポート窓口に問い合わせる
- 学校のICT支援員に相談する(いる場合)
💡 オンライン学習の継続は「植物の水やり」
オンライン学習を続けることは、「植物に水をやる」ことに似ています。毎日同じ時間に適量の水(学習時間)をやることで、植物(学力)は少しずつ成長します。水をやりすぎる(長時間学習を強制)と根腐れ(燃え尽き)し、水が少なすぎる(不規則)と枯れます。子どもの様子を見ながら、ちょうど良い量を続けることが大切です。
出席扱いを受けるための手続き
手続きの流れ
必要な書類(一般的な例)
- 学習計画書:何を、どのように学習するかの計画
- 学習記録:日々の学習内容と時間の記録
- 教材の資料:使用する教材の説明資料
- 保護者の同意書:保護者が学校と連携することの同意
※学校により求められる書類は異なります。必ず事前に確認してください。詳しくは出席扱い制度の7要件の記事もご参照ください。
⚠️ 学校によって対応が異なる
出席扱いの判断は校長に委ねられているため、学校によって対応が大きく異なります。積極的に認める学校もあれば、慎重な学校もあります。まずは担任に相談し、学校の方針を確認してください。もし学校が消極的な場合は、教育委員会に相談する方法もあります。
よくある質問(FAQ)
オンライン学習だけで高校に進学できますか?
はい、できる場合があります。出席扱いが認められれば、内申書の欠席日数が減り、高校進学に有利になる可能性があります。また、通信制高校、定時制高校、高卒認定試験など、多様な進学ルートがあります。不登校経験者の約85%が高校等に進学しています。
オンライン学習の費用は補助されますか?
基本的には自己負担ですが、一部の自治体では不登校児童生徒向けのオンライン学習費用の補助制度を設けている場合があります。お住まいの市区町村の教育委員会に問い合わせてください。また、通信制高校の場合は、高等学校等就学支援金制度が利用できます。
タブレットやパソコンがないのですが
多くの学校では、GIGAスクール構想により一人一台の端末が配布されています。不登校の場合でも、学校に相談すれば端末を借りられる可能性があります。また、一部の自治体では不登校児童生徒向けに端末の貸与制度があります。まずは学校に相談してください。
無料のオンライン学習サービスはありますか?
はい、あります。NHK for School(NHKの教育番組)、経済産業省「未来の教室」など、無料で利用できるコンテンツがあります。ただし、出席扱いを目指す場合は、学校の教育課程に沿った計画的な学習プログラムが求められるため、有料の体系的な教材の方が適している場合が多いです。
オンライン学習を始めたら、学校に戻れなくなりませんか?
そうとは限りません。オンライン学習は、「学校に戻るための準備期間」として活用できます。自宅で学習を続けることで学力を維持し、自信を取り戻すことができます。また、文部科学省も「学校復帰のみを目標としない」としており、オンライン学習で社会的自立を目指すことも認められています。焦らず、子どものペースで進めてください。
兄弟姉妹がいて、静かな環境が作れません
完璧な環境でなくても大丈夫です。ヘッドホンやイヤホンを使う、家族が静かにする時間帯を決める、部屋の一角をカーテンで仕切るなど、工夫次第で学習環境は作れます。また、図書館など公共施設の利用も検討してください。
まとめ:自宅でも学べる時代
この記事では、不登校・発達障害のある児童生徒向けのオンライン学習について解説しました:
- オンライン学習の3つのタイプ:教材型、ライブ授業型、個別指導型
子どもの学習スタイルに合わせて選べます。
- 出席扱い制度の7要件:文部科学省通知(令和元年10月25日)
一定の要件を満たせば、自宅学習が出席扱いになる可能性があります。
- 代表的な教材:すらら、スタディサプリ、天神など
発達障害に対応した機能が充実しています。
- 発達障害別の適した機能:音声読み上げ、短時間学習、視覚的教材
一人ひとりの特性に合わせた学習が可能です。
- 無料体験を活用:子ども自身に使ってもらう
実際に試してから決めることが大切です。
オンライン学習は、学校に代わる選択肢ではなく、子どもを支える一つの手段です。学校復帰を目指す場合も、別の道を選ぶ場合も、オンライン学習は学びを継続する力になります。
まずは、お子さんと一緒に無料体験を試してみてください。そして、学校に相談し、出席扱いの可能性を確認してください。学びを止めない選択肢が、今はたくさんあります。
その他の支援については、教育支援センターや発達障害者支援センターもぜひご活用ください。また、高校卒業後の進路についてはハローワークの専門支援もあります。
詳しくは発達障害と不登校の包括的な支援ガイドをご覧ください。